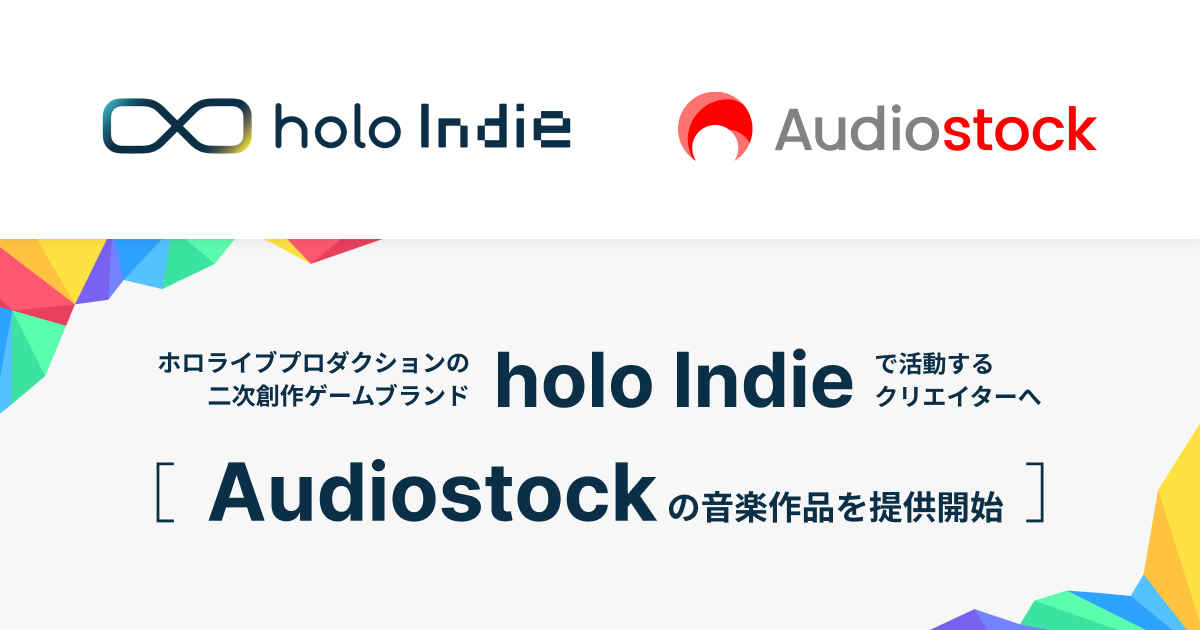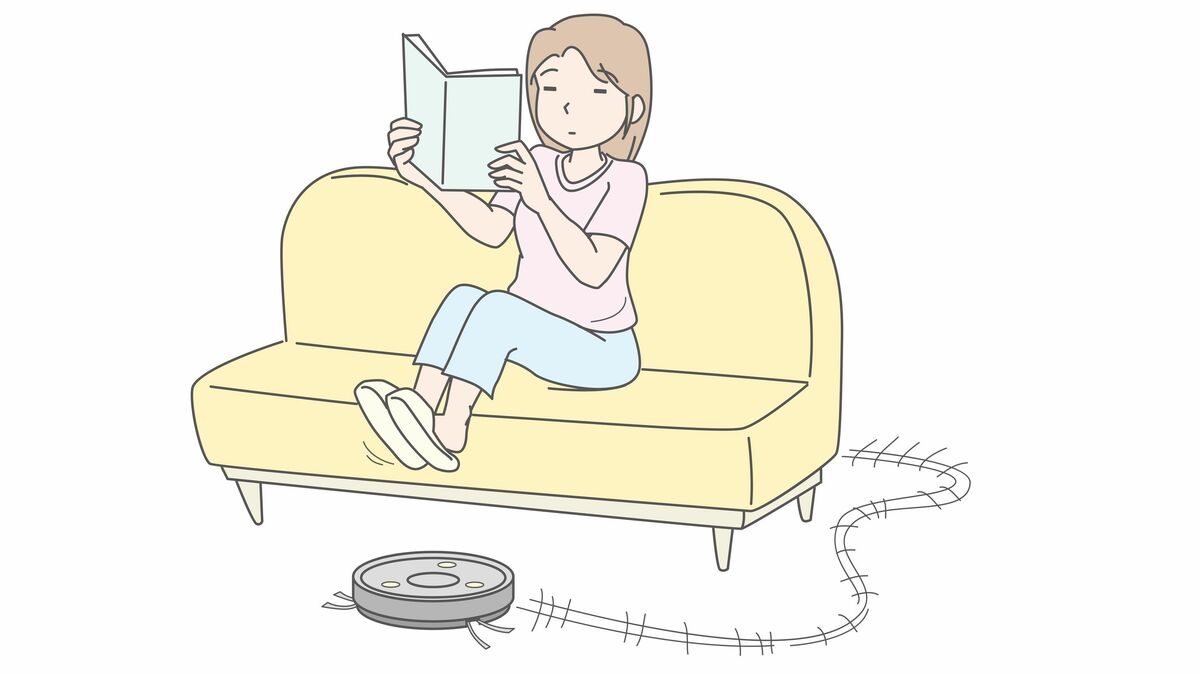ジャパニーズウイスキー人気がニュースになって久しいが、世界的にもウイスキー人気が高まっている。
そんな中、アメリカで、通常2年はかかる熟成期間を、わずか30時間で完了させたバーボンが登場した。いったいどんなバーボンなのか?その超時短熟成技術とは?
きっかけは宇宙航空機エンジニアの「なんでこんなに時間がかかるの?」
アメリカのウイスキー消費量は年々増加。米国スピリッツ協会(DISCUS)によると、2021年の消費量は2003年比で170%も伸びている。
アメリカンウイスキーといえばバーボンだ。主原料の穀物のうちトウモロコシを51%以上含み、80℃以下で蒸溜し、内側を焦がしたホワイトオークの樽で熟成させたウイスキーをバーボンと呼ぶ。2年以上熟成させたものが「ストレートバーボンウイスキー」と呼ばれ、日本で「バーボン」と言えば、ほぼこれのことだ。
バーボンというと、ストレートでグイッとあおるようなワイルドなイメージがあるが、近年はハイボールもポピュラー。カクテルのベースとしても用いられ、楽しみ方は多様化している。
そんな中、バーボンの本場アメリカで、熟成期間30時間という、にわかには信じがたいバーボンが現れた。
開発したのは、アメリカ・カリフォルニア州のベンチャー企業、BarrelRM社のショーン・ケリー氏。もともとは宇宙航空機や自動車のエンジニアだったショーン氏、バーボンについてはことさらマニアではないが、ごく気軽に飲むカジュアル派だ。あるときふと、「なぜバーボンをつくるのに何年もかかるのだろう?」と疑問が浮かんだ。航空機や車など、進化いちじるしい技術畑で腕をふるってきたエンジニアの好奇心が騒いだようだ。「テクノロジーの力でもっと短くできないだろか?」と思い立ち、熟成行程の時短研究に取りかかった。
 BarrelRMのバーボン熟成所は約30m²と小規模。左に見えるのは熟成タンク。特別なものではなく、一般的に流通しているタンクを使用している。
BarrelRMのバーボン熟成所は約30m²と小規模。左に見えるのは熟成タンク。特別なものではなく、一般的に流通しているタンクを使用している。
 樽熟成の代わりに使う、焦がしたホワイトオークのチップ。どれだけ焦がせばいいか、試行錯誤を繰り返した。オーク材のチップ以外、何も添加していない。
樽熟成の代わりに使う、焦がしたホワイトオークのチップ。どれだけ焦がせばいいか、試行錯誤を繰り返した。オーク材のチップ以外、何も添加していない。
7年間の樽の中の変化を早送りしたみたいな超時短熟成法
ショーン氏が開発した超時短熟成法に使われる原料や設備は、特別なものではない。原料は一般的に流通しているバーボン原酒。バーボンと言えば「樽で寝かせる」ものだが、樽は使わない。代わりに、焦がしたホワイトオークのチップを熟成用タンクに入れて浸漬させる。そして温度や湿度、酸素濃度などを微調整しながら熟成させること30時間。
30時間で熟成と呼ぶかどうかは意見が分かれるだろうが、ショーン氏によると、「7年間オーク樽で熟成させたのと同じ環境変化」が加えられたことになるという。タンクの中で7年間分の樽熟成が早送りされているイメージである。
開発には5年以上がかかったという。アメリカには多様なバーボン原酒が存在する。そのどれを採用するのか。樽代わりのウッドチップにはどのオーク材を採用し、それをどれだけ焦がすか。最大の難関は、タンク内の環境の調整である。これこそが超時短熟成法の肝になる。その一連の設計“レシピ”を考案し、調整はプログラミングされて全自動で行われている。遠隔操作も可能だ。
アメリカでは過去にも、小さな樽を使って熟成期間を短期化したり、オーク材のスティックをバーボンに浸けて熟成感をマシマシにしたりする方法などがあることはあった。しかし、BarrelRMのバーボンは、テクノロジーの力を駆使した、まったく新しいアプローチだ。
 BarrelRMの30時間熟成バーボン「The Factory American Whiskey 」。アルコール分47%。750ml:7500円/375ml:3900円(いずれも参考小売価格) ※バーボンはウイスキーの一種。バーボンと表示していないのは、2年以上熟成したストレートバーボンではないから
BarrelRMの30時間熟成バーボン「The Factory American Whiskey 」。アルコール分47%。750ml:7500円/375ml:3900円(いずれも参考小売価格) ※バーボンはウイスキーの一種。バーボンと表示していないのは、2年以上熟成したストレートバーボンではないから
さて、30時間で熟成したバーボンのお味は?
グラスに注ぐと、甘い香りと木のスモーキーな香りが立ち上る。樽熟成らしい香りだ。味はやや甘め、若々しさを感じる。2年以上熟成されたストレートバーボンと比べるのは難しいが、これはたしかにバーボンの味。ハイボールにすれば、スッキリした飲み心地が楽しめる。
日本の輸入元である有限会社ヤマダの山田瑠璃子さんは、この超時短熟成バーボンの価値を、「ウイスキー人気の高まりで、バーボンの品薄傾向も続いています。バーボンはいくら需要があっても、すぐに生産できるものではありません。最近はハイボールやカクテルで楽しむ人が増えていますが、それらのベースに2年以上も熟成させたバーボンを使うのはちょっともったいないとも言えるわけです。短期間でできるバーボンがあるなら、それを試す価値は十分あると思います」と語る。
 「THE FACTORY」をベースにしたハイボール缶も製品化。355ml:600円(参考小売価格)
「THE FACTORY」をベースにしたハイボール缶も製品化。355ml:600円(参考小売価格)
酒飲みも考えてみよう!持続可能なバーボンとは?
もうひとつ見逃せないのが、生産工程における環境コストの低さだ。あまり注目されていないところだが、バーボンの製造に、どれほどの環境コストがかかっているのだろうか?
BarrelRM社が、あるメーカーが伝統的な熟成方法で生産したバーボン7年分のコストと、自社の超時短熟成法による7年分のコストをシミュレーションしたデータがある。それによると、超時短熟成は伝統的な熟成方法に対して、電力消費量13.7%、CO2排出量13.6%と大幅に低減。7年分の樽倉庫の空調管理費などが節約できるからである。
使用する原酒の量は、13.2%と試算されている。ウイスキー(バーボン)は熟成中に毎年2~3%が揮発していく。「天使のわけまえ」と呼ばれる蒸発分だが、超時短熟成なら蒸発もしない。
原酒が少なく済むことから、原料のトウモロコシの農地面積は13.2%と試算されている。樽に使われるホワイトオークの木材量に至っては、なんと1.1%。近年、ホワイトオーク林の保全についての意識も高まっている。環境負荷の観点からすると、超時短熟成で造られる酒の優秀である。
超時短熟成法はバーボンに限らず、ラムやテキーラなどにも応用できる。今、世界的に人気上昇中のRTD製品の多くに使われるスピリッツ類の生産にも、超時短熟成は有効だろう。
酒は嗜好品であるから味もイメージも大事だが、愛好家の心を満たす贅沢な酒と、原材料としての酒、使い分けできるなら、それはそれで合理的だ。超時短熟成のバーボン(広くはウイスキー)は最短2日でできるのだから、オンデマンドでの供給も可能だ。使い分けが進めば、長期的に見るなら、従来の伝統的なウイスキー価格の安定化に寄与するのではないだろうか。
伝統的な樽熟成のバーボンとは趣を異にする、新しい酒が生まれる可能性もある。開発者のショーン氏によると、「テクノロジーの進化によっては、50年熟成相当のバーボンを2日でつくれるようになるかも」とのこと。それはいつの日になるかわからないが、バーボンをカジュアルに飲みたい派には、一度、「THE FACTORY」をトライしてみてほしい。それが今、世界最先端のバーボンの味だ。
The Factory Spirits
BarrelRM
Instagram
取材・文/佐藤恵菜