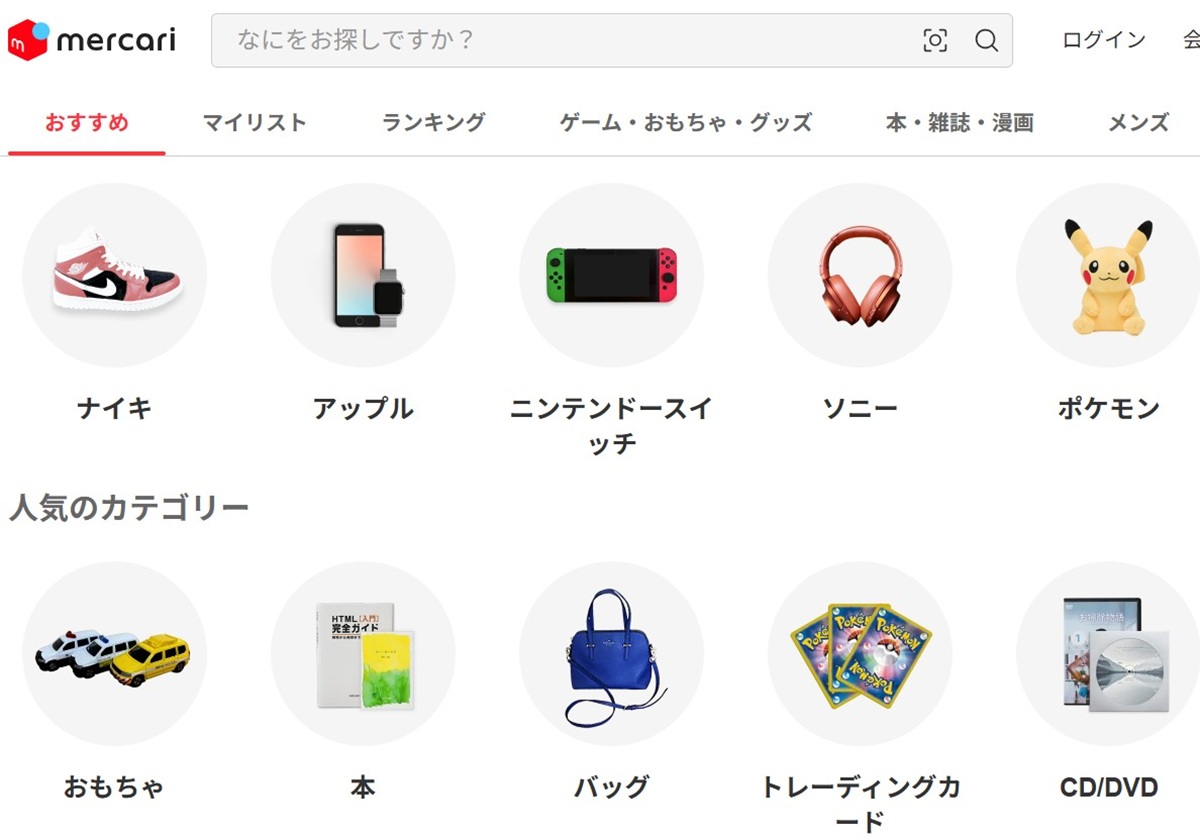企業の経営者や幹部の方からよくお聞きする悩みが「部下育成」です。時代の変化から「〇〇世代だから感覚が違いますね?」というような質問も頂きます。部下にどのような声をかければよいのか?指摘したらパワハラになってしまうのではないか?など、部下への指摘自体に躊躇しておられる管理職の方からのご相談も増えています。今回は上司が行う部下への指摘にスポットをあてて部下育成の解説をしていきたいと思います。
部下への指摘はしてよいのか?
部下への指摘はもちろんしてもよいです。むしろしなければいけません。例えば社内のルールを守っていない部下がいれば指摘して守らせることが、上司としてまず重要な役割です。指摘をするのが難しいと感じておられる管理職の方がいれば見直してほしいのは、そのルールが守れているかいないかが、〇×で判別できるようなルール設定になっているかどうかです。そもそも解釈が人によって異なるような曖昧なルールの場合、指摘する側とされる側とでその解釈に違いがあります。その状態で指摘をしても、「私は守っているつもりです」などルール解釈をめぐっての押し問答になってしまいます。明確なルール設定の上で、守らなければいけないことが出来ていない場合は指摘する必要があります。このように必ず指摘しなければいけないことも存在をしています。
一方で部下育成の指摘として思い浮かぶのは、部下が思うような成長をしない・うまくいかない時等にどのような指摘をすればよいのかということだと思います。部下育成において重要なのは、【部下の成長に繋がる指摘】がでてきているかどうかです。上司側がどのような指摘をするかによって、部下の成長に影響が出てくるということです。
部下の成長とは?
部下が成長しない!とおっしゃる方に私が必ずお聞きするのは、どんなふうに成長してほしいかの具体像です。何ができるようになってほしいのかを尋ねると、「もっと上を目指してほしい、自分で考えて動いてほしい」などの答えが返ってくることがあります。先日も、育成像を掘り下げていくと「〇〇ができるようになってほしい」等の具体的な内容が出てきたので、「それは部下に伝えていますか?」と尋ねました。すると「言葉で言ってはいないが、それくらいは分かっていると思う」という答えが返ってきたのです。実際に部下にもインタビューをしてみると、上司がもとめていることとは全然違った内容に、上司の方は愕然とされていました。どんな成長をすればよいのか、どうなれば成長なのか、皆さまの部下の方には伝わっているでしょうか?
まずは部下育成という言葉が指し示す中身の認識が上司と部下で合っているのか、これが第一ステップとして重要です。どこに進むか分からずに人は集中して頑張ることはできません。役割・果たすべき目標を部下が理解しているかどうか、上司とイメージがあっているかの認識を合わせましょう。これを踏まえた上で、部下を【成長させる指摘】と【成長を止めてしまう指摘】に分けて考えいきます。
成長を止めてしまう指摘とは?
部下の成長を妨げてしまう指摘の多くは、感情的であったり、具体性に欠けていたり、相手に不必要なストレスを与える特徴があります。以下に、その代表的な例と理由を5つを紹介します。
1. 感情的な指摘
例: 「何でこんな簡単なこともできないんだ!」「いい加減にしろ!」
感情に基づいて叱責するだけでは、具体的に何を改善すべきかが相手に伝わりません。部下は「改善」よりも「叱られた恐怖」に意識が向いてしまい、部下の成長に繋がりません。
2. 抽象的すぎる指摘
例: 「もっと頑張って」「ちゃんとやってよ」
何をどのように改善すればよいのかが不明確なため、部下は次に自分がとるべき具体的な行動に結びつけられないため、結果的に同じミスを繰り返す可能性が高くなります。
3. 人格批判を含む指摘
例: 「君には向いてないよね」「本当にやる気あるの?」
行動や業務ではなく、部下の人格や能力そのものを否定してしまう指摘です。自信を喪失させてしまい、業務の改善を考える行動には繋がりません。
4. 他人と比較する指摘
例: 「○○さんはちゃんとできているのに、君はどうしてできないの?」
他人との比較は部下の自己肯定感を傷つけ、嫉妬や不満など負の感情を生みます。比較すべきは他人ではなく、部下自身が追いかけた目標と結果です。余計なプレッシャーを与えるだけとなり、本来集中すべき目標への意識が低下します。
5. 過去の失敗を繰り返し掘り返す指摘
例: 「前にも同じことを言ったよね」「また同じミスか!」
過去の失敗を繰り返し指摘することで、部下は「改善より責められている」という印象を受けます。また過去をいくら指摘しても起きたことは変えられません。変えていくべきは未来です。
成長させる指摘とは?
部下を成長させる指摘は部下が「不足を認識する」ことです。できていないことや足りていないものを把握することは、成長への基本的な要素です。人は理想と現実のギャップに自身では気づきにくいものです。成長するためには客観的な評価が必要不可欠です。これをふまえて、以下に成長させる指摘のポイントを5つ紹介します。
1. 役割と責任に基づいた指摘
部下のミスや改善点を指摘する際には、感情的な表現を避け、部下の「役割」に基づいて説明します。部下が自分の役割や責任に対しての不足を理解し、改善につなげることができます。
2. 事実ベースで話す
主観や感情ではなく、具体的な事実を示して伝えます。具体的であるほど、相手も受け入れやすく、改善に向けて動きやすくなります。
3. 感情を排除した冷静な伝え方
指摘を行う際、叱る・怒るなどの感情を交えないようにし、「結果に対する事実」と「未来へ向かっての行動変化」にフォーカスします。
4. 評価の枠組みを明確にする
部下にどのような基準で評価されているのかを明示し、その基準に沿った形で指摘します。目標と評価基準が明確であると、部下は自分がどこを改善すべきかを理解しやすくなります。
5. 指示を明確化し、曖昧さを排除
部下が迷わないよう、次に取るべき行動を具体的に指示します。
• NG例: 「気をつけてやっておいて。」
• OK例: 「次回からは作業後に〇〇チェックリストを使用して確認してください。」
まとめ
今回は【部下への指摘】に着目をして部下育成を考えてきました。部下育成は上司にとって主たる役割の一つになっている方も多いでしょう。どんな指摘をするかということを考えるためにも、改めて上司としてどのような部下育成が必要なのかを振り返ってみてくだい。チームを率いる上司として部下に求めている役割、その役割は本当に部下に伝わっているでしょうか?部下が理解できているかどうかは、部下の行動にあらわれます。「わかりました」という言葉で理解できたと済ませるのではなく、部下の行動が止まっている・迷っているようであれば伝わっていない可能性が高いのです。部下の目標を明確にし、動き出したら、不足やズレのあった行動に対して指摘を行いましょう。この指摘は決してダメ出しやつめるということではありません。不足を認識し、未来を変えるにはどうすればよいかを部下自身に考えさせます。これをとにかく繰り返して回数を重ねていくことが部下の成長を管理していくということに繋がります。上司の指摘は部下を成長に導いていきます。不足に向かうその瞬間は部下自身にとっても困難があるかもしれません。「指摘したら悪いかな」と今の心地よさを選ぶことは本当に部下のためになるでしょうか?今、指摘しないことが【部下の成長機会を奪う】可能性がある、ということを今回のまとめとしたいと思います。
文/株式会社識学 川添晶美