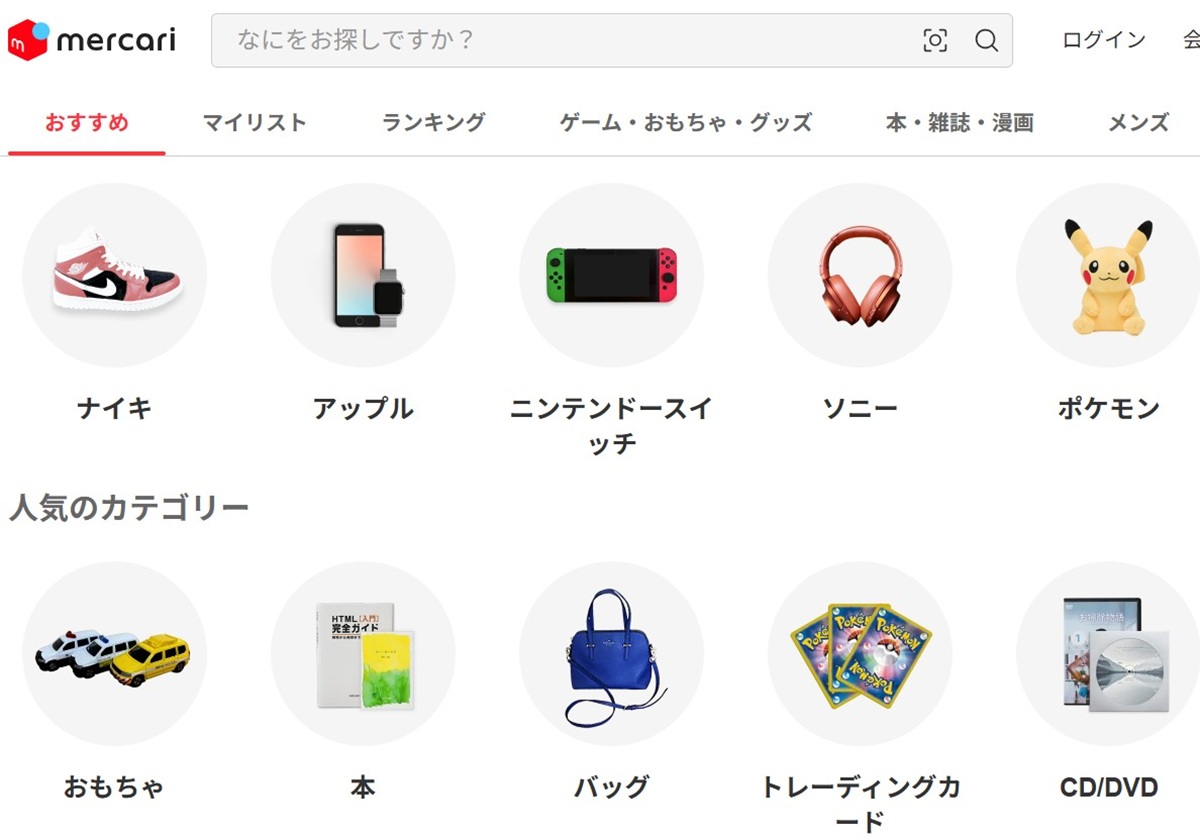「社畜」とは、「会社に飼いならされた家畜」のように働く人を揶揄する言葉と言われることが多い。
„Åó„Åã„ÅóÂÆüÈöõ„Å´„ÄåÁ§æÁïú„Å®„ÅØ„ÄÅ„Éê„ǧ„Éà„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÇÇÂê´„Åæ„Çå„Çã„ÅÆ„ÅãÔºü„Äç„ÄåÁ§æÁïú„Å®„ÅØ„ÄÅÁ∞°Âçò„ŴˮĄÅÜ„Å®„Å©„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜÊÑèÂë≥„Å™„ÅÆ„ÅãÔºü„Äç„Å™„Å©„ÄÅÊ∞ó„Å´„Å™„ÇãÁÇπ„ÅØ„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„ÅÝ„ÄÇ
‰ºöÁ§æ„Å∏„ÅÆÈÅéÂ∫¶„Å™ÂøÝ˙݄ÅåÁæéÂæ≥„Å®„Åï„Çå„ÇãÈ¢®ÊΩÆ„ÅØ„ÄÅÊôÇ„Å´Èï∑ÊôÇÈñìÂä¥ÂÉç„ÇÑÂøÉË∫´„ÅÆÁñ≤ºä„Å´„ŧ„Å™„Åå„Çä„ÇÑ„Åô„ÅÑ„ÄÇÊú¨Ë®ò‰∫ã„Åß„ÅØ„ÄÅÁ§æÁïú„ÅÆÁâπÂ楄ÇфǪ„É´„Éï„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„ÄÅÊäú„ÅëÂá∫„Åô„Åü„ÇÅ„ÅÆÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å™ÂØæÁ≠ñ„Å™„Å©„ÇíË©≥„Åó„ÅèËߣ˙¨„Åô„Çã„ÄÇ
社畜とは何か?その意味を簡単に解説
„ÄåÁ§æÁïú„Äç„Å®„ÅØ„Å©„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜÊÑèÂë≥„Åã„ÄÅ„Å®Â∞ã„Å≠„Çã„٧ö„Åè„ÅƉ∫∫„Åå„Ä剺öÁ§æ„Å´È£º„ÅÑ„Å™„Çâ„Åï„Çå„ÄÅ„Åæ„Çã„ÅßÂÆ∂Áïú„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´ÂÉç„Åã„Åï„Çå„ÇãÁ§æÂì°„Äç„Å®„ÅÑ„Å܄ǧ„É°„ɺ„Ç∏„ÇíÊåńŧ„ÅÝ„Çç„ÅÜ„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„ÄÅÈï∑ÊôÇÈñìÊÆãÊ•≠„ÅåÂ∏∏ÊÖãÂåñ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Çä„ÄÅÊúâÁµ¶‰ºëÊöá„ÇíÂèñÂæó„Åó„Å•„Çâ„Åã„Å£„Åü„Çä„Åô„ÇãÁä∂Ê≥Å„Å´ÁñëÂïè„ÇíÊåÅ„Åü„Åö„ÄÅ„Åü„ÅÝÂæìÈÝÜ„Å´ÂÉç„ÅçÁ∂ö„Åë„ÇãÂßø„ÅåÊè∂ÊèÑ„Åï„Çå„Çã„ÄÇ
„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅÆÁîüÊ¥ª„ÇÑÊÑèÂøó„ÇíÁäÝÁâ≤„Å´„Åó„Ŷ‰ºöÁ§æ„Å´Âæì„ÅÜÁä∂Ê≥Å„ÇíÊåá„Åó„Ŷ„ÄåÁ§æÁïú„Äç„Å®Â뺄Å∂„DZ„ɺ„Çπ„Åå§ö„ÅÑ„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅÁ§æÁïú„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ÄËëâ„ÅÆÊàê„ÇäÁ´ã„Å°„ÇÑ„ÄÅÊó•Êú¨ÁâπÊúâ„ÅÆÂä¥ÂÉçÊñáÂåñ„Å®„ÅÆÈñ¢ÈÄ£„ÇíÊ预ţ„Ŷ„Åø„Çã„ÄÇ
‚ñÝÁ§æÁïú„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ÄËëâ„ÅÆÊàê„ÇäÁ´ã„Å°„Å®‰Ωø„Çè„ÇåÊñπ
„ÄåÁ§æÁïú„Äç„ÅØ„Ä剺öÁ§æÔºàÁ§æÔºâ„Äç„Å®„ÄåÂÆ∂ÁïúÔºàÁïúÔºâ„Äç„ÇíÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„ÅüÈÄÝË™û„Åß„ÄÅ„Éç„ÉÉ„Éà„Çπ„É©„É≥„Ç∞„Å®„Åó„ŶÂ∫É„Åæ„Å£„Åü„ÅÆ„ÅåÂßã„Åæ„Çä„ŮˮĄÇè„Çå„Çã„ÄljºöÁ§æ„Åã„Çâ„Åô„Çå„Å∞„ÄåÈ£º„ÅÑ„Å™„Çâ„Åó„ÅüÁ§æÂì°„Äç„ÄÅÁ§æÂì°„Åã„Çâ„Åô„Çå„Å∞„ÄåÂÆ∂Áïú„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´ÁÑ°Âäõ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Éã„É•„Ç¢„É≥„Çπ„ÅåÂê´„Åæ„Çå„ÄÅÁöÆËÇâ„ÇÑËá™ËôêÁöÑ„Å™ÊÑèÂë≥„ÇíÊåńŧ„ÄÇ
一方で、この言葉が注目される背景には、過酷な労働環境や長時間労働を黙々とこなす働き方が社会問題化している現状がある。
ËᙄÇâ„Çí„ÄåÁ§æÁïú„Äç„Å®Ëá™Ëôê„Åô„Çã‰∫∫„ÇÇ„ÅÑ„Çå„Å∞„ÄÅÂë®Âõ≤„Åå„Äå„ÅÇ„ÅƉ∫∫„ÅØÁ§æÁïú„ÅÝ„Äç„Å®Êè∂ÊèÑ„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çã„Å™„Å©„ÄʼnΩø„Çè„ÇåÊñπ„ÅØ„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„ÅÝ„ÄÇ
‚ñÝÊó•Êú¨„ÅƉºÅÊ•≠ÊñáÂåñ„Å®Á§æÁïú„ÅÆËÉåÊôØ
Êó•Êú¨ÁâπÊúâ„ÅƉºÅÊ•≠ÊñáÂåñ„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÁµÇË∫´ÈõáÁÇÑÂπ¥ÂäüÂ∫èÂàó„ÅåÈï∑„ÅèÁ∂ö„ÅÑ„ÅüÊ≠¥Âè≤„Åå„ÅÇ„Çä„ÄʼnºöÁ§æ„Å∏„ÅÆÂøÝË™ÝÂøÉ„ÇíÁæéÂæ≥„Å®„Åô„ÇãÈ¢®ÊΩÆ„ÅåÊÝπ‰ªò„ÅфŶ„Åç„Åü„ŮˮĄÇè„Çå„Çã„ÄÇË≤¨‰ªªÊÑü„Åƺ∑„Åщ∫∫„Åå§ö„Åè„ÄÅ„Ä剪ï‰∫ã„ÇíÊñ≠„Çã„ÅÆ„ÅØÊÇ™„Äç„Å®„ÅÆÂøÉÁêÜÁöÑ„Éè„ɺ„Éâ„É´„ÇÇÂ≠òÂú®„Åô„Çã„ÄÇ
‰æã„Åà„Å∞„Äʼn∏äÂè∏„ÅåÂ∏∞„Çã„Åæ„ÅßÈÄÄÂ㧄Åó„Å•„Çâ„ÅÑÈõ∞Âõ≤Ê∞ó„ÇÑ„ÄʼnºëÊó•„Å´„ÇÇË°å‰∫ã„Å∏„ÅÆÂèÇÂäÝ„Çíº∑„ÅÑ„Çâ„Çå„ÇãÁøíÊÖ£„Å™„Å©„Åå„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅÂæìÊ•≠Âì°„Å؉ºöÁ§æ„Ŵ§ö„Åè„ÅÆÊôÇÈñì„Å®Âä¥Âäõ„ÇíÊçß„Åí„Åå„Å°„Å´„Å™„Çã„ÄÇ
その結果、「社畜」のように自分の自由や健康を後回しにする働き方が生まれると考えられる。
社畜の特徴とバイトにも当てはまる注意点
「社畜」というと正社員のイメージが強いかもしれないが、実は非正規のバイトやパートでも同様の状態に陥る可能性がある。
例えば、バイト先で休日がほとんどない、シフトの調整が一方的で休みづらいなど、劣悪な勤務環境から逃れられずにいると、それも「バイト版社畜」と言えるかもしれない。
ここでは、社畜と呼ばれる働き方の代表的な特徴と、バイトにも共通するリスクについて見てみよう。
‚ñ݉ª£Ë°®ÁöÑ„Å™Á§æÁïú„ÅÆÁâπÂæ¥
„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅÁ§æÁïú„Å®Êè∂ÊèÑ„Åï„Çå„Çã‰∫∫„Å´ÂÖ∏ÂûãÁöÑ„Å™„Éù„ǧ„É≥„Éà„ÇíÁ¥π‰ªã„Åô„Çã„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅʨ°„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÈÝÖÁõƄŴ§ö„ÅèÂΩì„Ŷ„ÅØ„Åæ„Çã„Å™„Çâ˶ÅÊ≥®ÊÑè„ÅÝ„ÄÇ
- Èï∑ÊôÇÈñìÊÆãÊ•≠„ÅåÂΩì„Åü„ÇäÂâçÔºöÊó©Êúù„Åã„ÇâÊ∑±Â§ú„Åæ„ÅßÂÉç„ÅфŶ„ÇÇ„ÄÅ„ÄåÈÝ뺵„Å£„ŶÂΩìÁÑ∂„Äç„Å®ÊÄù„ÅÑË溄Çì„Åß„ÅÑ„Çã„ÄÇ
- 仕事を最優先しがち:休日出勤やサービス残業を断らないため、プライベートの時間がほとんどない。
- 会社や上司に逆らえない:不合理な指示でも疑問を持たず、受け入れてしまう。
„Åì„Çå„Çâ„Å´ÂÖ±ÈÄö„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØ„Äʼnªï‰∫㉪•Â§ñ„ÅÆÈÅ∏ÊäûËÇ¢„Åå˶ã„Åà„Å™„Åè„Å™„Çä„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅÆÁîüÊ¥ª„ÇíÁäÝÁâ≤„Å´„Åó„Ŷ„Åß„ÇljºöÁ§æ„Å´Âæì„ÅÜÂßøÂ㢄Ååº∑„ÅÑÁÇπ„ÅÝ„ÄÇ
‚ñÝ„Éê„ǧ„Éà„Åß„ÇÇÁ§æÁïúÂåñ„Åó„ÇÑ„Åô„ÅÑÁä∂Ê≥Å„Å®„ÅØ
バイトであっても次のような状況が常態化しているなら、社畜的な働き方に陥る可能性がある。
- 無理なシフト変更に応じ続ける:急な呼び出しや希望を超えた出勤要請にも断りきれず、休みが取れない。
- Ëæû„ÇÅ„ÇãËá™ÁÅå‰∫ãÂÆü‰∏ä•™„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„ÇãÔºö„Äå‰∫∫Êâã‰∏çË∂≥„ÅÝ„Åã„ÇâËæû„ÇÅ„Çâ„Çå„Åü„ÇâÂõ∞„Çã„Äç„ŮˮĄÇè„Çå„ÄÅÈÄÄËÅ∑„ÇíÂàá„ÇäÂá∫„Åõ„Å™„ÅÑ„ÄÇ
- ËÅ∑ÂÝ¥Áí∞¢ɄŴÂïèÈ°å„Åå„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÇÇÁõ∏Ë´á„Åß„Åç„Å™„ÅÑÔºö•ëÁ¥ÑÊúüÈñì„ÅåÁü≠„ÅÑ„ÄÅÁ´ãÂÝ¥„Å庱„ÅÑÁêÜÁÅã„Çâ„ÄÅÊîπÂñÑ„ÇíʱDŽÇÅ„Å•„Çâ„ÅÑ„ÄÇ
„Éê„ǧ„Éà„ÅÝ„Åã„Çâ„Åì„Åù„ÄÅÊ≠£Á§æÂì°„Å®ÊØî„Åπ„ŶÂæÖÈÅáÊîπÂñÑ„ÅÆ˶ÅʱDŽÅå„Åó„Å´„Åè„Åè„ÄÅÊäú„ÅëÂá∫„Åô„ÅÆ„ÅåÈõ£„Åó„ÅфDZ„ɺ„Çπ„ÇÇ„ÅÇ„Çã„Åü„ÇÅÊ≥®ÊÑè„Åó„Åü„ÅÑ„ÄÇ
社畜チェックで自分の働き方を振り返る
Ëá™ÂàÜ„Åå„ÄåÁ§æÁïú„Äç„Åã„Å©„ÅÜ„Åã„ÇíÂà§Êñ≠„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØÁ∞°Âçò„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅÂƢ˶≥Áöфř˶ñÁÇπ„Åß˶ã„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„ÄåÁ§æÁïúÂ∫¶„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„Äç„ÇÑ„ÄåÁ§æÁïú„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„É™„Çπ„Éà„Äç„ÇíÊ¥ªÁÅó„Ŷ„Åø„Çã„ÅÆ„Å؉∏Ąŧ„ÅÆÊñπÊ≥ï„ÅÝ„ÄÇ
§ö„Åè„ÅÆÈÝÖÁõÆ„Å´ÂΩì„Ŷ„ÅØ„Åæ„Çã„Ū„Å©„ÄʼnºöÁ§æ„Å´ÊåØ„ÇäÂõû„Åï„Çå„ÇãÂÉç„ÅçÊñπ„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÅåÈ´ò„Åæ„Çã„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅØ„Äʼnª£Ë°®ÁöÑ„Å™„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØÈÝÖÁõÆ„Å®„ÄÅÁµêÊûú„ÅåÁ§∫„Åô„É™„Çπ„ÇØ„ÇÑÂØæÂá¶Ê≥ï„Å´„ŧ„ÅфŶËߣ˙¨„Åô„Çã„ÄÇ
‚ñ݄Ǫ„É´„Éï„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØÈÝÖÁõÆ„ÅƉæã
‰ª•‰∏ã„Å´Á§∫„Åô„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØÈÝÖÁõÆ„Å´‰ΩïÂÄãÂΩì„Ŷ„ÅØ„Åæ„Çã„ÅãÁ¢∫Ë™ç„Åó„Ŷ„Åø„Çã„Åì„Å®„Åß„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅåÁ§æÁïúÂÇæÂêë„Å´„ÅÇ„Çã„Åã„Å©„ÅÜ„Åã„Åä„Åä„Çà„ÅùÊääÊè°„Åß„Åç„Çã„ÄÇ
- 休日でも会社からの連絡にすぐ応じてしまう
- 有給休暇を取得するのが気まずい、罪悪感がある
- 周囲が残業していると先に帰りづらい
- 仕事以外の趣味や目標が特にない
- 長時間労働について「仕方ない」と諦めている
„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„Åå§ö„ÅфŪ„Å©Á§æÁïúÁä∂ÊÖã„Å´Ëøë„ÅфŮˮĄÅà„Çã„Åå„ÄÅË©≥„Åó„Åè„ÅØÁµêÊûú„ÇíË∏è„Åæ„Åà„ÄÅʨ°„Å´Á¥π‰ªã„Åô„ÇãÂØæÂá¶Ê≥ï„ÇÑ„É™„Çπ„ÇØ„Å®„Å®„ÇÇ„Å´ËÄÉ„Åà„Çã„Åì„Å®„Åå§ßÂàá„ÅÝ„ÄÇ
‚ñÝ„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØÁµêÊûú„Åã„ÇâËÄÉ„Åà„Çã„É™„Çπ„ÇØ„Å®ÂØæÂá¶Ê≥ï
Á§æÁïú„ÅÆÁä∂ÊÖã„ÅåÈï∑„ÅèÁ∂ö„Åè„Å®„ÄÅËÇâ‰ΩìÁöфɪÁ≤æÁ•ûÁöÑ„Å´Áñ≤ºä„Åó„ÄÅÊúÄÊÇ™„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØ„Å܄ŧÁóÖ„Å™„Å©„ÅÆÂøÉË∫´Áóá„Å´Èô•„ÇãÊÅê„Çå„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ
‚ñÝ„É™„Çπ„Ç؉æã
- Áù°Áú݉∏çË∂≥„ÇщΩìË™ø‰∏çËâØ„ÅÆÊÖ¢ÊÄßÂåñ
- 家族や友人との関係悪化
- 仕事へのモチベーションが低下し、パフォーマンスも落ちる
‚ñÝÂØæÂá¶Ê≥ï„ÅƉ∏ĉæã
- ËÅ∑ÂÝ¥Áí∞¢ɄÇíÊîπÂñÑ„Åô„Çã„Çà„Å܉∏äÂè∏„Å´Áõ∏Ë´á„Åô„Çã
- 勇気を持って有給休暇の申請や休暇取得を行う
- 業務量が過多なら同僚や上司と調整し分担する
こうした対処を試みることで、社畜状態を軽減できる可能性がある。
社畜になりやすい人が陥りがちな考え方
Á§æÁïúÁä∂ÊÖã„Å´Èô•„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÄÅÂçò„Å´‰ºÅÊ•≠È¢®Âúü„Çщ∏äÂè∏„ÅÆ„Åõ„ÅÑ„ÅÝ„Åë„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÄÇÊú¨‰∫∫„ÅåÊåńŧÊÄßÊݺ„Çщæ°Âħ˶≥„Çǧ߄Åç„ÅèÂΩ±Èüø„Åô„Çã„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅÊñ≠„Çã„ÅÆ„ÅåËã¶Êâã„ÅÝ„Å£„Åü„ÇäË≤¨‰ªªÊÑü„Ååº∑„Åô„Åé„Åü„Çä„Åô„Çã„Å®„ÄŧöÂ∞ëÁÑ°Áê܄ř˶ÅʱDŽÅß„ÇÇÂèó„ÅëÂÖ•„Çå„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÑ„Åå„Å°„ÅÝ„ÄÇ
ここでは、社畜になりやすい人のメンタリティをもう少し詳しく見てみよう。
‚ñÝÊñ≠„Çå„Å™„ÅÑÊÄßÊݺ„Ů˩ï‰æ°‰æùÂ≠ò„ÅÆÁΩÝ
„Äå‰æã„Åà„Å∞„ÄÅÈݺ„Åø„Åî„Å®„ÇíÊñ≠„Çã„Ů´å„Çè„Çå„Çã„ÅÆ„Åß„ÅØ„Äç„Äå‰∏äÂè∏„Åã„Çâ„ÅÆË©ï‰æ°„Åå‰∏ã„Åå„Çã„ÅÆ„Åß„ÅØ„Äç„ÄåÂë®Âõ≤„Å´Ëø∑ÊÉë„Çí„Åã„Åë„Åü„Åè„Å™„ÅÑ„Äç„Å®„ÅÑ„Å£„Åü‰∏çÂÆâ„Åã„Çâ„ÄÅ„Å©„Çì„řʕ≠Âãô„ÇǺï„ÅçÂèó„Åë„Ŷ„Åó„Åæ„Å܉∫∫„ÅØ„ÄÅÁ§æÁïúÂåñ„ÅÆ„É™„Çπ„ÇØ„ÅåÈ´ò„ÅÑ„ÄÇ„Åù„Åó„ŶÁµêÊûúÁöÑ„Å´„ÄÅÁ≤æÁ•ûÁöÑ„Å´„ÇÇËÇâ‰ΩìÁöÑ„Å´„ÇÇÁñ≤ºä„ÅåÂãü„Çã„ÄÇ
‚ñÝË≤¨‰ªªÊÑü„Åƺ∑„Åï„ÅåÁîü„ÇÄÁõ≤ÁÇπ
責任感が強いこと自体は悪いことではない。しかし、過度な責任感ゆえに「自分がやらねば誰もできない」と思い込み、仕事を抱え込み続けるケースがある。
„Åæ„Åü„ÄÅ„Ä剺öÁ§æ„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´ÁäÝÁâ≤„ÇíÊâï„Å£„ŶÂΩìÁÑ∂„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÄùËÄÉ„Å´Èô•„Çã„Å®„ÄÅÂÆ∂Êóè„ÇÑËá™ÂàÜËá™Ë∫´„ÅÆÂÅ•Â∫∑„Çí„Å™„ÅÑ„Åå„Åó„Çç„Å´„Åó„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÜÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇÁµêÊûúÁöÑ„Å´Êú¨‰∫∫„ÅåË㶄Åó„ÇÄ„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅÂë®Âõ≤„Å®„ÅÆ„Ç≥„Éü„É•„Éã„DZ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Å´„ÇÇÊÇ™ÂΩ±Èüø„ÇíÂèä„ź„Åó„ÄÅÂ≠§Á´ãÊÑü„ÅåÈ´ò„Åæ„Çã„É™„Çπ„ÇØ„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ
社畜あるあるや「社畜ニート」の背景

SNSなどを中心に、「社畜あるある」というフレーズが盛り上がることがある。そこでは、忙しすぎる生活や勤務先の理不尽さを自虐的に笑い合う文化が見られる。
また、「社畜ニート」という一見矛盾しているような言葉もときどき目にする。ここでは、社畜あるあるの典型例や「社畜ニート」が示す背景について整理する。
‚ñÝ„Çà„ÅèËÅû„ÅèÁ§æÁïú„ÅÇ„Çã„ÅÇ„Çã„ÅƉæã
社畜あるあるとして挙げられる現象には、次のようなものが多い。
- 帰宅すると疲れすぎて風呂にも入れず寝落ちする
- 上司がいるかぎり絶対に退勤できない
- 「忙しい」が口癖なのに、なぜ忙しいか分からなくなっている
‚ñÝÁüõÁõæ„ÇíÂê´„ÇÄ„ÄåÁ§æÁïú„Éã„ɺ„Éà„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜË°®Áèæ
„Äå„Éã„ɺ„ÉàÔºàNEETÔºâ„Äç„ÅØÂÉç„ÅфŶ„Åä„Çâ„Åö„ÄÅÂ∞±Â≠¶„ÇÑËÅ∑Ê•≠Ë®ìÁ∑¥„ÇÇÂèó„Åë„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åщ∫∫„ÇíÊåá„Åô„Älj∏ÄÊñπ„Åß„ÄåÁ§æÁïú„Äç„ÅØ„Äʼnªï‰∫ã„Å´ËøΩ„Çè„ÇåÈÅé„Åé„ÇãÂÉç„ÅçÊâã„ÇíÁöÆËÇâ„ÇãË®ÄËëâ„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÄÅÊú¨Êù•„ÅØÂØæÊ•µ„Å´„ÅÇ„Çã„ÅØ„Åö„ÅÝ„ÄÇ
しかし「社畜ニート」は、以下のような意味合いで使われることがある。
- 社畜経験を経て無気力化し、退職してニート状態になった
- ‰ºöÁ§æ„Å´„ÅØÂú®Á±ç„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åå„ÄÅÂÆüË≥™ÁöÑ„Å´ÊàêÊûú„ÇíÂá∫„Åõ„Ŷ„Åä„Çâ„Åö‚ÄúÁÑ°ÁÇ∫„Å´‚ÄùËÅ∑ÂÝ¥„Å´ÈÄö„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã
いずれもSNS上でのスラング的用法が中心で、学術的な定義はないものの、働き方の歪みや苦悩を表す言葉として注目されることがある。
英語では何と言う?社畜をめぐる海外の表現
日本の「社畜」に相当する英語表現を探してみると、「wage slave」や「corporate slave」などがスラングとしてよく挙げられる。
„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅʨßÁ±≥„ÅÆÂä¥ÂÉç˶≥„ÇÑÊñáÂåñ„ÅØÊó•Êú¨„٧߄Åç„ÅèÁï∞„Å™„ÇãÁÇπ„Çǧö„ÅÑ„Åü„ÇÅ„ÄÅÂçò„Å´Áõ¥Ë®≥„Åô„Çã„ÅÝ„Åë„Åß„ÅØ„Éã„É•„Ç¢„É≥„Çπ„Å剺ù„Çè„Çä„Å´„Åè„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„Å؉ª£Ë°®ÁöÑ„Å™Ëã±Ë™û„Çπ„É©„É≥„Ç∞„ÇÑʵ∑§ñ„ÅÆÂÉç„ÅçÊñπ„Å®„ÅÆÈÅï„ÅÑ„Çí˶ã„Ŷ„Åø„Çà„ÅÜ„ÄÇ
‚ñ݉ª£Ë°®ÁöÑ„Å™Ëã±Ë™û„Çπ„É©„É≥„Ç∞
„Äåcorporate slave„Äç„Äåwage slave„Äç„ÅØ„ÅÑ„Åö„Çå„ÇÇ„ÄʼnºöÁ§æ„ÇÑË≥ÉÈáë„Å´Á∏õ„Çâ„Çå„ÄÅËá™ÁÅå„Å™„ÅÑÊßòÂ≠ê„ÇíÊè∂ÊèÑ„Åô„ÇãËã±Ë™ûË°®Áèæ„ÅÝ„ÄÇ
- “corporate slave”:企業(corporate)の奴隷(slave)
- “wage slave”:給料(wage)のために働かされる奴隷
‚ñÝʵ∑§ñ„Å®„ÅÆÂÉç„ÅçÊñπ„ÅÆÈÅï„ÅÑ
欧米圏ではワークライフバランスを重視する企業が多いとされ、休暇や残業規制もしっかり守られる傾向がある。そのため、日本ほど「社畜」的な状態は目立たないという意見もある。
„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅ„Ç∞„É≠„ɺ„Éê„É´‰ºÅÊ•≠„ÅÆÁ´∂‰∫â„ÅåÊøÄ„Åó„ÅÑÁè扪£„Åß„ÅØ„ÄÅʵ∑§ñ„Åß„ÇÇÈÅéÈáçÂä¥ÂÉç„Å´Ë㶄Åó„Çĉ∫∫„ÅØ¢ó„Åà„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®ÊåáÊëò„Åô„Çã£∞„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇÁµê±ĄÅÆ„Å®„Åì„Çç„ÄÅ„ÄåÁ§æÁïú„Äç„Åå„Å©„Åì„Åæ„Åßʵ∏ÈÄè„Åô„Çã„Åã„ÅØÊñáÂåñ„ÇÑË®ÄË™û„Å´„Çà„Å£„Ŷ„Çǧâ„Çè„Çã„Åå„ÄÅÂÉç„Åç„Åô„Åé„ÇíÁöÆËÇâ„ÇãË°®Áèæ„ÅØ„ÅÑ„Åö„Çå„ÅÆÂõΩ„Åß„Çlj∏ÄÂÆöÊï∞Â≠òÂú®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ
‚ĪÊÉÖÂݱ„Å؉∏áÂÖ®„ÇíÊúü„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Åå„ÄÅÊ≠£Á¢∫ÊÄß„Çí‰øùË®º„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
文/編集部