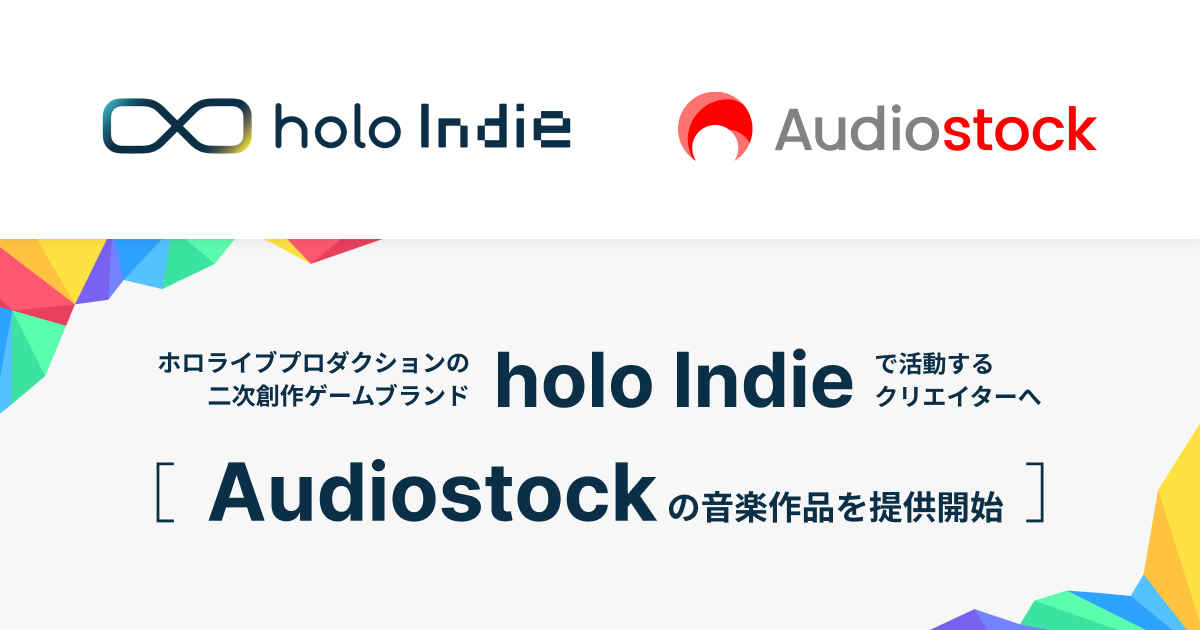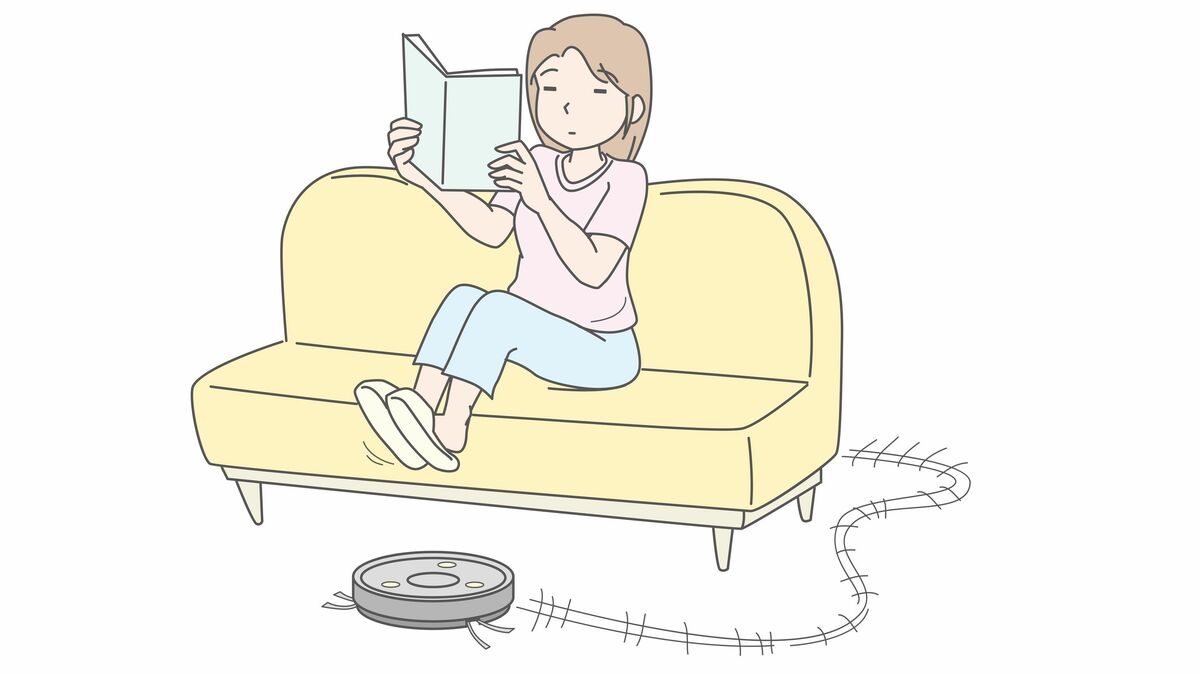東京大学安田講堂で開催されたいすゞ自動車と東京大学による「トランスポートイノベーション研究センター」開設記者会見で、まず目を奪われたのが、いすゞ自動車が寄付したという10億円という金額です。少なくない、どころかたいへんな数字です。なぜにして、そこまでして。いすゞ自動車が求める日本の知とは何なのでしょう。
安定した、恒久的、持続的な活動を行なう「エンダウメント型研究組織」へ
産学共同とは昨今頻繁に行われている取り組みですが、その多くは期間限定だといいます。たとえば3年、5年といった具合にスタート~ゴールが設定される中での研究となり、またそのために採用される研究者は多くが非常勤です。産学となれば一定の明瞭な研究成果を出す必要が求められるため、比較的小粒な、言い換えれば、定められた期間内に成果、結果を提出できる研究内容になりがち。むろん、締め切りが無ければ作家が書かないのと同様(?)、ある一定のゴール設定は必要ですが、ゴールから逆算してできる範囲の研究になってしまうのでは、本末転倒もいいところです。
ところが今回の取り組みは、その資金運用からして意欲的、そして持続的です。
というのも、いすゞ自動車の寄付金10億円を東京大学が一般市場で運用し、その運用益でもって、長期にわたり、大胆に研究を行える環境づくりを整えようとしているのです。今回のような「エンダウメント型研究組織」によってより安定した、恒久的、持続的な活動を狙うわけです。この「エンダウメント型研究組織」の開設は、東京大学と一般企業との間では初とのこと。(ちなみに一番最初のエンダウメント型研究組織の開設は昨年の10月で、なんと個人の寄付によるものです!)
本センター設立にあたり、いすゞ自動車が期待するものは3つある、と同社、片山正則CEOは言います。
まず「持続可能な形で物流効率化や人手不足を解決する糸口を見つける」こと、次いで「まだ見ぬ将来の物流・交通の姿を見える化する」こと、最後に「いすゞ自動車が2030年に目指す姿である「商用モビリティソリューションカンパニー」をリードする人財の育成」です。
余談ですが、片山CEOの母校がここ東京大学とのことで、このたび安田講堂で開催された記者会見自体、氏にとって感慨深い時間であったとか。故郷に錦ならぬ、母校に錦というわけでしょう。
ネットショッピングが日常手段となり、買い物は「行く」に加え「届けられる」ものになっています。増える一方の取扱荷物に対して、人手不足、環境負荷低減、安全安心の担保、これらを解決する自動運転や環境技術を含めたその先の見通しは、研究によるシミュレーションと実験の出番です。一台の自動車作りの知見をはるかに超えた、広い範囲を処理しなくてはならないのですから。
商用車を手掛けるいすゞ自動車が一歩先、いや、三歩先の物流、交通の姿を俯瞰したいと考えるのは当然なことで、そこに東京大学の総合知とタッグを組む大きな価値があります。登壇者たちの発言の中に幾度か、ビッグビジョン、という言葉がのぼりました。自由に、大胆に、大局的な見地から物流課題を解決に導く研究を、とのメッセージと理解しました。今回のエンダウメント型研究組織設立は、このビッグビジョンを達成するための一手なのです。
本センター の研究が、日本はもとより、地球物流イノベーションにヒントをもたらすかも知れないと思えば、これは期待せずにいられません。なぜならこの“ビッグビジョンな”研究は、直接、わたしたち自身の快適便利な物流生活の、その継続・発展のカギを握っているのですから。
 力強さと笑顔がぴたりシンクロする両者。いすゞ 会長CEO 片山正則氏(左)と東京大学総長 藤井輝夫氏 。
力強さと笑顔がぴたりシンクロする両者。いすゞ 会長CEO 片山正則氏(左)と東京大学総長 藤井輝夫氏 。
文/前田賢紀