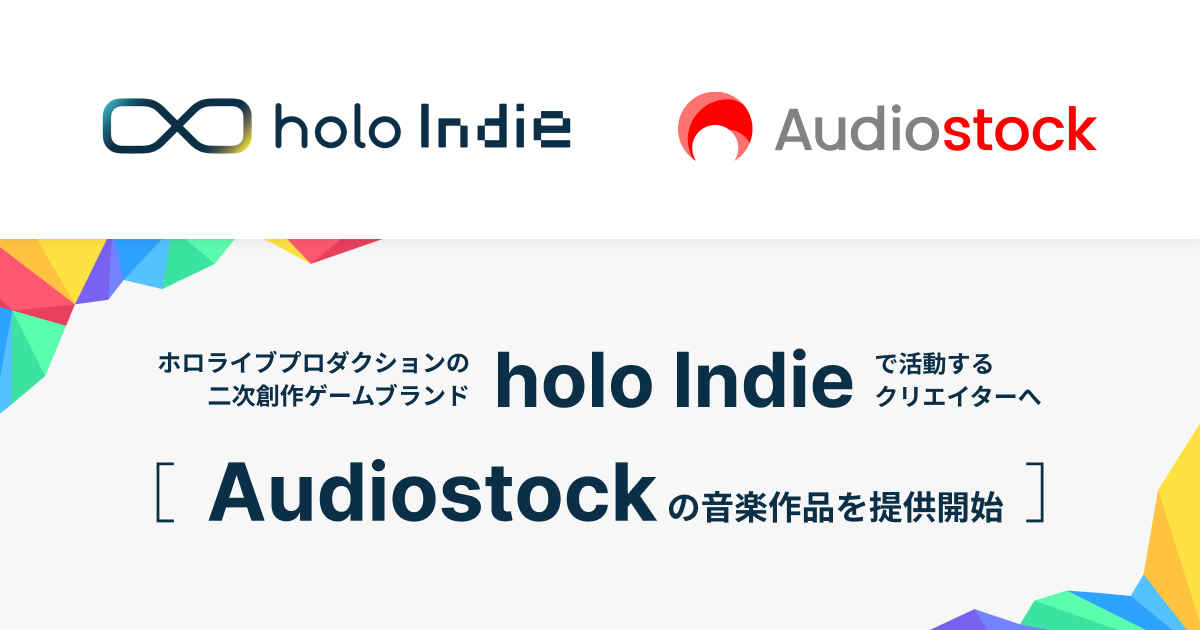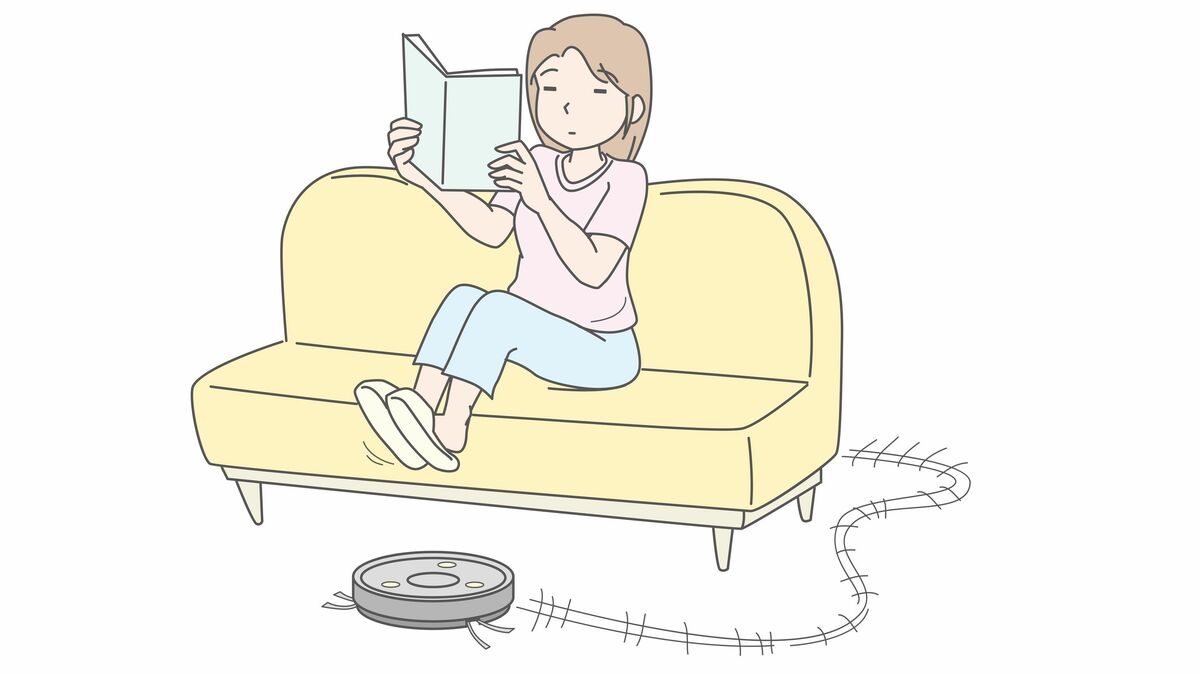発達障害のある人やグレーゾーンの人は、抜群の記憶力を持っていたり、アイデアが豊富に出てくるといった強みがある一方で、場の空気を読むことやルーティンワークが苦手といった困りごとを抱えている。そのような部下が自分のもとに配属された場合、彼らに対してどう接し、どのように指導すればよいのだろう。
心理学者・カウンセラーで公認心理師・精神保健福祉士・博士(ヒューマン・ケア科学/筑波大学大学院博士課程修了)であり、株式会社メンタルシンクタンク(筑波大学発ベンチャー)副社長の舟木彩乃先生に、グレーゾーンの部下に対する対応の仕方について、教えてもらった。
グレーゾーンとは、発達障害の傾向がありながら、その診断がついていない人たちを指す。定型発達(注1)から発達障害までを白から黒のグラデーションとみた場合、両者の間にあるグレーの領域が「グレーゾーン」と呼ばれているが、グレーゾーンという診断名は存在していない。明確な線引きができないために、グレーゾーンは発達障害以上に正確に定義することが難しいと舟木先生は言う。
実際にグレーゾーンの部下を持った場合、どのような点に注意したらいいのだろう。舟木先生が提案する5つのポイントは、新刊書「発達障害グレーゾーンの部下たち」(SBクリエイティブ発刊、定価1045円)に詳しく解説されている。
ポイントその1:ハラスメントにならない注意の仕方を身につける
グレーゾーンの部下は、ダメな所を何度注意しても直らない傾向があると言う(そうでないケースもある)。こうしたケースでは、上司は「自分の考え方や教え方が悪いのか」と思って悩む場合と、「一生懸命指導しているのに、態度を改めない部下に困る」と苛立ってしまう場合の2つのパターンに分かれる。
舟木先生によると、特にパワーハラスメントに発展しやすいのは後者の上司で、他の部下より時間をかけて指導しているのに、グレーゾーンの部下にだけ頻繁にミスが起きている状態に頭を抱え、怒りを覚えてしまうのだという。
また、指示をメモさせて何回も見返すように伝えても、グレーゾーンの部下は「どこにメモしたかを忘れてしまいました」あるいは「急いでメモしたので字が読み見にくくて判読できません」と言い返してくることもあり、上司は困ってしまうようだ。こうしたことが何回も繰り返されると、ついカッとなって声を荒げてしまったり、激高してしまう上司もいる。
一方で、グレーゾーンの部下の立場からすると、「悪気があって上司を困らせているわけではないし、自分なりに一生懸命頑張っている」にもかかわらず、「自分に対してだけいつも上司は当たりが強く、もしかすると上司は自分を嫌っているのではないか」と感じてしまう。結果的に、これはパワーハラスメントに当たるかもしれないと誤解してしまうのである。
グレーゾーンの部下をもったら、まず「ハラスメントにならない伝え方」をしっかり身につける必要がある。部下に対して怒るのではなく、部下と一緒に対策を考えること。どんなことに困っているのかを一緒に考えているという気持ちを伝えることが重要であると、舟木先生はアドバイスしている。
さらに具体的なアドバイスとして1)我を忘れて怒鳴り散らさないように、口を閉じて沈黙を維持する、2)その場で深呼吸し、怒りがおさまるまで6秒間待つ、3)怒りに限らずネガティブな感情が起きたらその場から立ち去る、という3つの解決策を提案してくれた。
ポイントその2:モチベーションを維持してもらう褒め方を身につける
グレーゾーンの人たちは、なぜ自分だけうまくいかないのかと疑問に思い、悩んでいることが多い。他の同僚がスムーズにできることも、なぜか自分はなかなかできない。さらに、また注意されたらどうしようと気を張っていることも多く、休日になるとヘトヘトで寝込んでしまう場合もある。こうした辛さを抱えているということを、上司は理解した上で、彼らのモチベーションを維持できるような褒め方を実践したい。
ミスを指摘する場合は「〇〇ができていません」という伝え方でなく、「××はできるようになりましたね、次の〇〇はこうしたらできるようになるのでは?」と、できていないことを指摘する前に、できるようになったことを先に伝えることがポイントである。
また、指摘をする場合は、提案も添えることが必要になる。たとえば、会議でグレーゾーンの部下の話が長引いてしまい、議長に注意されてしまったとする。そのような場合、グレーゾーンの部下はどこが悪かったのか、どうしたらよかったのかを理解できていないことも多い。そのため、会議の終了後に本人に対して具体的に何が良かったのか、どこがダメだったのかを伝えるようにするとよい。先に良かった点を伝えておくことで、安心感を与えることができる。その後に今後どうしたらよいか提案する内容を伝えれば、グレーゾーンの部下も安心して指摘を受け入れることができる。
グレーゾーンの部下にはアフターフォローをこまめにすることで、本人のモチベーション維持につながることが多い。部下のできることや、困っていることについての理解ができれば、徐々に任せて良い仕事も見えてくる。上司の負担も軽くなるはず。
ポイントその3:コミュニケーションが円滑になる声掛けをする
多くのグレーゾーンの人が抱えている悩みの1つに職場での雑談がある。 ASD特性(注2)をもつグレーゾーンの人は、対人関係において感情共有などが苦手で共感力が乏しかったり、自分の気持ちをあまり伝えられないという特性がある。また、独自のマイルールにこだわったり、臨機応変なコミュニケーションが苦手という特性を持っている人もいる。
ADHD(注3)の特性を持つグレーゾーンの人たちは、上司など重要な人の話をじっと聞いていることが難しかったり、喋りすぎたり、頭の中に浮かんだことがすぐに口に出てしまうといった傾向がある。彼らは、自分では自覚していながらもコントロールが難しく、どうしたらいいのか分からないこともあるようだ。
舟木先生によると、こうした傾向があるからといって、全員がコミュニケーションに困っているわけではないと言う。ただし、「職場でもっと会話がしたい」と考えている部下については、こうした特性があることを把握し、適度な声かけをすることで、コミュニケーションがスムーズに行くことも多い。
また、仕事を円滑に進めるためには、グレーゾーン特有の辛さを理解した上で、彼らが陥りがちなパターンへの対応法をあらかじめ用意しておくことが大切になる。例えばほかの部下であれば「手が空いている時にこの書類を簡単にまとめておいて」という指示で通じることもあるだろう。しかし、グレーゾーンの部下に対して、こうした曖昧な指示はNGである。
「仕事の締切は何時まで、この書類のこの部分を、これを参考にして、このように仕上げてくれませんか?」というように、すべて指示は具体的に出すこと。そして本人が認識している完成形と、上司が考えている完成形が最終的に合致しているかどうか、一つずつ見直す。このような伝え方を身につけておくことは、グレーゾーンの部下に限らず、ほかのメンバーとの仕事も円滑に進むことに繋がるだろう。
グレーゾーンはマイルールや規則にこだわる人、仕事でもマニアックな細部にこだわる人が多い。上司としては部下とのコミュニケーションにおいて自分の思い通りの展開にならない場合でも、過剰に反応し、怒りなどの感情に左右されないよう、コントロールしていくことが重要となる。
仕事でマニアックな細部にこだわってしまう場合は、全体像を見せた上で、一つ一つの仕事にかけられる時間を提示し、どの部分にフォーカスして欲しいかについてきちんと説明し、時間配分を共有することで、こだわりから脱することができる。
さらにグレーゾーンの部下のなかには、仕事の優先順位が付けられない人も多い。全体と部分の把握が難しいため今後の展開が予測しにくい、途中で何か別の用件が入ってしまうと今やっていることを忘れてしまうといった特性を持つからである。こうしたトラブルを防ぐためには、1週間ごともしくは1日のはじめに、一緒にTO DOリストを作成し、定期的にチェックすることがおすすめだという。重要度が高い順にメモをし、終わったら削除することを繰り返せば、仕事の達成感を得ることもできる。