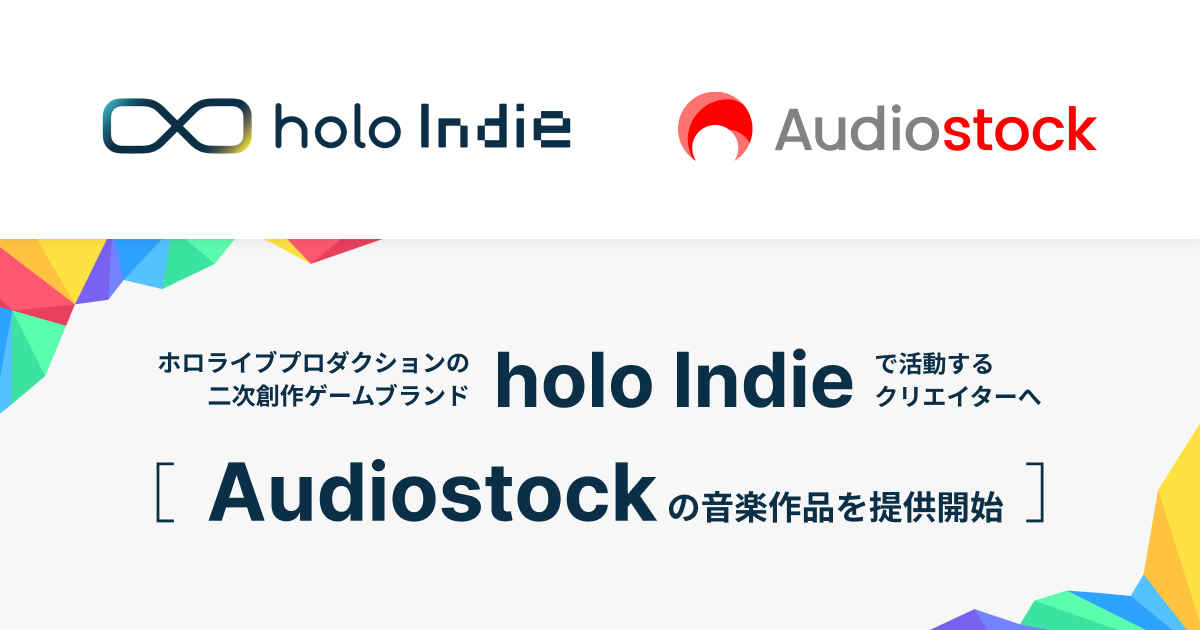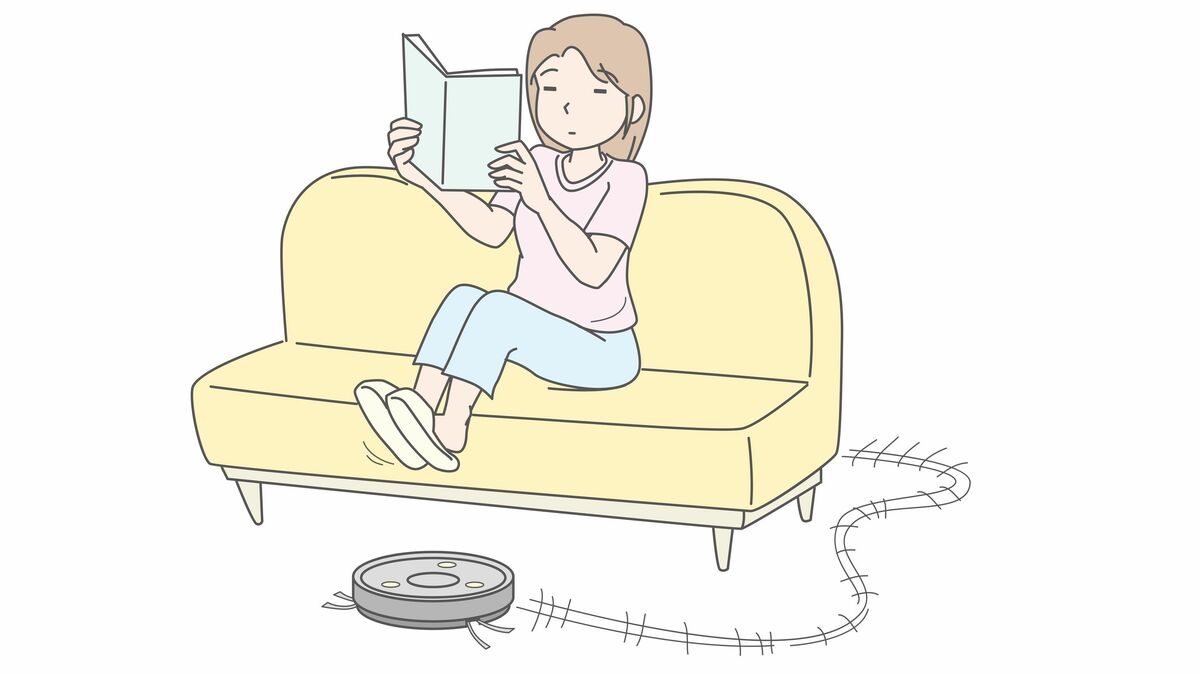「齟齬」とは
 「齟齬」とは「そご」と読み、物事がうまく噛み合わないことや、食い違いなどを意味する言葉です。お互いの認識のズレから、物事が円滑に進まなくなることを意味します。
「齟齬」とは「そご」と読み、物事がうまく噛み合わないことや、食い違いなどを意味する言葉です。お互いの認識のズレから、物事が円滑に進まなくなることを意味します。
ビジネスシーンで「齟齬が生じている」といった表現などで使われるため、意味を正しく理解しておきましょう。
参考:デジタル大辞泉
「相違」との違い
 齟齬と混同しやすい言葉として、「相違(そうい)」が挙げられます。相違とは、2つのものの間に明確な違いがあることをあらわす言葉です。一方、齟齬は認識がズレていたりがうまく噛み合っていなかったりする状態を指します。
齟齬と混同しやすい言葉として、「相違(そうい)」が挙げられます。相違とは、2つのものの間に明確な違いがあることをあらわす言葉です。一方、齟齬は認識がズレていたりがうまく噛み合っていなかったりする状態を指します。
したがって、「意見や認識の違い」を意味する点は同じですが、そもそも明らかに一致しないのか、認識のズレによるすれ違いが起きているのかという点が異なります。
ここからは、それぞれの言葉を用いた会話例をみていきましょう。
■齟齬の状態をあらわす会話例
齟齬の状態をあらわした会話例は、以下のとおりです。
A「明日の会議の議題は確認していますか?」
B「もちろん。新しいプロジェクトのスケジュール案を固める予定ですよね?」
A「いや、私は予算について話すものだと理解していましたが」
B「それは、認識に齟齬があるようですね。確認しておいたほうがよさそうです」
■相違の状態をあらわす会話例
相違の状態をあらわす会話例は、以下のとおりです。
A「先日議論したマーケティング戦略についてどう考えますか?」
B「私はターゲット層に相違があると思います。若年層をターゲットにしたほうが効果的ではないでしょうか」
A「そうなんですね。私は中高年層をターゲットにする戦略には賛成でした。考え方の相違がありますね」
B「それでは、それぞれのターゲット層についてもう少しデータを集めて、検証しましょう」
ビジネスシーンにおける「齟齬」の使い方と例文
 齟齬は、認識のズレが生じている状態や、行動面で行き違いが起きている状態をあらわす言葉です。ビジネスシーンで認識のズレと行動面でのズレが生じている場合について、それぞれの齟齬の使い方を解説します。
齟齬は、認識のズレが生じている状態や、行動面で行き違いが起きている状態をあらわす言葉です。ビジネスシーンで認識のズレと行動面でのズレが生じている場合について、それぞれの齟齬の使い方を解説します。
■認識にズレが生じている場合
・新しいプロジェクトの進め方について、メンバー間で認識に齟齬が生じているため、再度目線合わせが必要だ
たとえばプロジェクトの進行にあたり、メンバー間の認識にズレが生じていると、プロジェクトが進むにつれてそのズレが大きくなることが懸念されます。結果的に、成功を妨げる要因となりかねません。そのような状況を避けるために、認識のズレが生じている状況を共通認識とすることを目的として、齟齬という言葉を使うことがあります。
■行動面で行き違いが起きている場合
・戦略チームとマーケティングチームの行動計画に齟齬が生じた原因は、情報共有が徹底されていなかったためだと考えられる
行動面における行き違いを、「齟齬が生じている」と表現することも少なくありません。異なる部門間の動きに齟齬が生じないようにするには、情報共有の場を設け、意思疎通を図っておく必要があるでしょう。
「齟齬」を使う際の注意点
 齟齬は、以下の点に注意して使用しましょう。
齟齬は、以下の点に注意して使用しましょう。
・目上の相手には使わない
・自分に非がある場合は使わない
それぞれの内容について解説します。
■目上の相手には使わない
齟齬は、取引先や上司などの目上の相手には使わないようにしましょう。少なからず相手にも認識のズレがあることを指摘するニュアンスが含まれており、批判的に受け止められてしまうリスクがあるためです。
相手の責任を追及するような印象を与え、不快感を抱かせてしまうと、今後の仕事に悪影響を及ぼしかねません。
■自分に非がある場合は使わない
自分に非がある場合も、齟齬という表現は使わないようにしましょう。齟齬は「相手と自分に認識のズレがある」という意味であるため、自分のミスによって行き違いが生じているにもかかわらず、相手にも非があると捉えている印象を与えてしまいます。それにより、「自分のミスを認めない人」というレッテルを貼られてしまう恐れがあることを、知っておく必要があります。
たとえば報告書の提出が遅れてしまった場合、「提出日に関する認識に齟齬がありました」と伝えるのではなく、素直に「提出日を誤って認識していました。申し訳ございません」と謝罪しましょう。