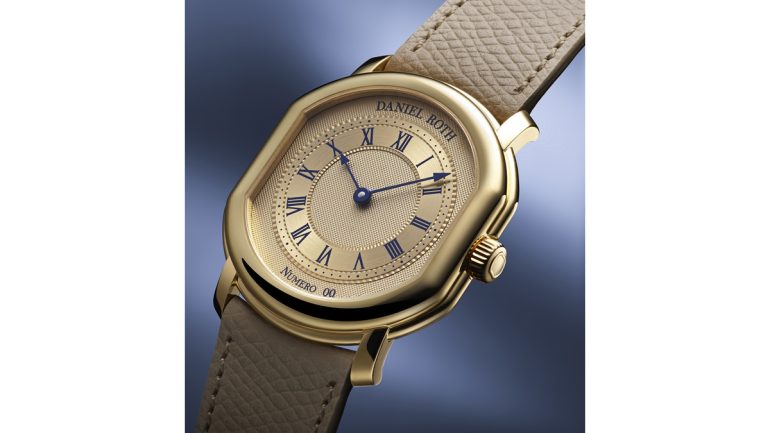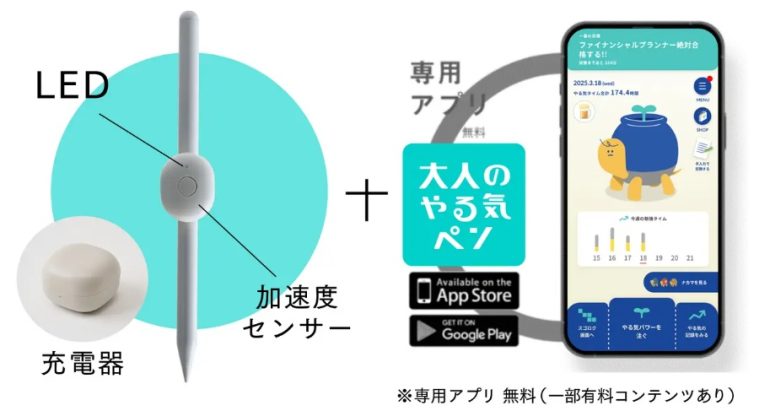近親者が亡くなって間もない時期、いわゆる「喪中(もちゅう)」の期間に初詣へ行っても良いのか気になる方は多いでしょう。
結論から先に言うと、喪中であっても新年のお参りに行けないわけではありません。ただし、留意したい点がいくつかあります。
喪中の初詣は、どのような点に注意すべきなのでしょうか。喪中の意味やお参りの際のタブー、年賀状やお年玉・お正月飾りはどうする?といった関連知識、さらには喪中の初詣におすすめの場所も紹介します。
初詣に行く前にチェックしたい喪中と忌中の違い

近親者が亡くなった場合、お祝い事を避けて静かに暮らします。この期間は『喪中』『忌中(きちゅう)』など呼ばれますが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。
まずは喪中と忌中の違いを明確に理解しておきましょう。
■喪中とは家族や近親者の死を弔う期間
近親者が亡くなると、その家族や親族は一定期間喪に服します。『喪中』とは、この服喪期間のことです。
『慎ましく暮らし、近しい者の死を弔う』という意味合いがあり、この期間中は慶事を避け、派手な遊びなども自重するのが一般的です。
喪に服すべきとされるのは、故人の2親等に当たる人までといわれます。つまり、故人と配偶者から数えて2世代までの関係にある人は、喪に服さねばなりません。
どのくらいの期間喪に服すかは、故人との関係性にもよります。親密な間柄なら長期間にわたって喪に服すこともありますし、そうでない場合は短くてすむケースもあるでしょう。ただし通常は『一周忌を迎えるまで』とすることが多いようです。
■忌中とは神道の『穢れ』が続く期間
一定期間喪に服して死者を弔うという点で、喪中と同じ意味合いがあります。ただし、喪中が一周忌を迎えるまで続くのに対し、忌中は1カ月半程度と、そこまで長くはありません。仏式なら四十九日の法要まで、神式なら五十日祭までと考えられています。
忌中の由来は『死は穢れ』と考えられていた時代の儀式に遡ります。当時は穢れが伝染すると考えられていたため、死に触れた人々は、社会的な係わりを断つ必要がありました。この考えが現代も引き継がれているのです。
純粋に死者を悼むために行われる喪中と比較して、より社会的な意味合いが強いといえるでしょう。
喪中は初詣に行くべきではない?

喪中にはお祝い事は避けるべきといわれます。それでは、新年のお参りである初詣に赴くことも避けたほうがよいのでしょうか。近親者が亡くなった場合の初詣について考えてみましょう。
■喪中の初詣はOK。ただし忌中は神社への参拝を控えるのがベター
喪中の期間内でも、神社・お寺とも初詣はできます。ただし、それが忌中に当たる場合は、神社への参拝は避けたほうが無難です。
神道では、死は『穢れ』となり、近親者を亡くした人は、忌中の間はこの穢れが残っていると考えられます。神社に住まう神様は穢れを嫌うため、穢れを持つ人が神社に近づくことは好ましくありません。
一方で、喪中はあくまでも故人を偲ぶための期間であり、死の穢れとは関係ありません。近親者が亡くなった場合でも、喪中の初詣は問題ないとされています。
ただし、『喪中は派手なことやお祝い事は避けるべき』というのが一般的です。初詣のお参りの際は晴れ着の着用は避け、三が日を外すなどの配慮をするのがベターでしょう。
■喪中の初詣の注意点1:「鳥居をくぐらなければいい」は間違い
「鳥居をくぐらなければ、人が亡くなってもお参りしてよい」と聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、前述のとおり、問題となるのはその人が『死の穢れを持っているかどうか』です。
その人が忌中であれば、鳥居をくぐろうがくぐるまいが、神社に近づくこと自体習わしに反します。逆に、忌中さえ過ぎていれば、鳥居をくぐっても問題はありません。
実際のところ、鳥居を避けるほうが神社参拝においてはマナー違反です。鳥居は神社の玄関のようなもので、鳥居を避けることは玄関から入らないのと同義と考えられます。参拝の際は、むしろきちんと鳥居をくぐることをおすすめします。
■喪中の初詣の注意点2:お守りやお札授与は忌明けに
せっかくの新年、新しい気持ちでお守りやお札をそろえたいのは当然ですが、これも忌中は避けねばなりません。
基本的にお札やお守りは、1年ごとに新調するのが好ましいといわれます。初詣には古いお守りやお札を携えて処分し、新しいものを購入しようと考える人も多いでしょう。
しかし、死の穢れを持つと考えられる人は、神社に近づくことができません。そのため、境内に入ってお守りやお札を求めるのも、当然避けたほうがよいでしょう。お守りやお札を授与してもらうのは、忌明けを迎えてからでも十分間に合います。
忌中に初詣をする場合はお寺へ

初詣に神社にお参りするのは、忌中の間は避けねばなりません。それでは、初詣にお寺をお参りするのはどうなのでしょうか。お寺への初詣については、仏教の教えを知ると可否がよく分かります。忌中のお寺へのお参りについて考えてみましょう。
参拝のベストな時間帯は?寺によって参拝の仕方に違いはある?これだけは覚えておきたいお寺の参拝ルール
由緒正しきお寺に行っても参拝の仕方がイマイチよくわからなくて困った経験がある人は、案外多いのではないだろうか。 寺は神社と違い、神様のいるところではなく、仏教の...
お寺での参拝時は、神社と同じように二礼二拍手一礼をすればよいのでしょうか。お寺の正しい参拝順序や作法の意味を知ると、より清々しい気持ちでご本尊と対面できます。参...
■お寺は喪中・忌中とも初詣をしても問題ない
喪中または忌中の人が初詣にお寺へ行くことは、特に問題ありません。
そもそも仏教において、四十九日の法要までが忌中といわれるのは『故人の行き先がこの日まで決まらない』という考えに基づきます。
仏教では、『人は亡くなると49日目に閻魔さまによって最後の審判を受ける』と考えます。このとき功徳が認められなければ、その人は極楽浄土へ行くことができません。
そのため、故人が極楽浄土へ行けるよう、近親者は亡くなった日から祈りを捧げ続けます。そして49日目の審判の日の法要をもって、これを終わりとします。仏教では、この期間を忌中と呼ぶのです。
仏教の考えは、死を穢れとする神道と大きく異なります。近親者が亡くなった人がお寺に初詣をしても、仏教ではタブーとはならないのです。
■喪中の初詣のマナー1:にぎやかな場所はなるべく避ける
初詣の期間中は、神社と同様に参拝客でにぎわうお寺がたくさんあります。このような場所は新年の喜びにあふれており、華やかな雰囲気が漂うでしょう。
しかし、忌中や喪中は、お祝いごとや派手な行動は慎むべきといわれています。にぎやかな場所はなるべく避け、静かにお参りしましょう。近親者の死を知る人が見れば、初詣や正月を祝う姿を不謹慎と考えるかもしれません。
■喪中の初詣のマナー2:ご先祖のお墓へ新年のご挨拶を
神社での初詣は、おみくじを引いたりお賽銭を入れたりするのが一般的です。
それではお寺はどうかというと、まずはご先祖さまのお墓に向かいます。真摯に手を合わせて新年のご挨拶をすれば、一年のよいスタートとなります。仏花など携えてお寺に行き、改めて故人の冥福をお祈りしましょう。