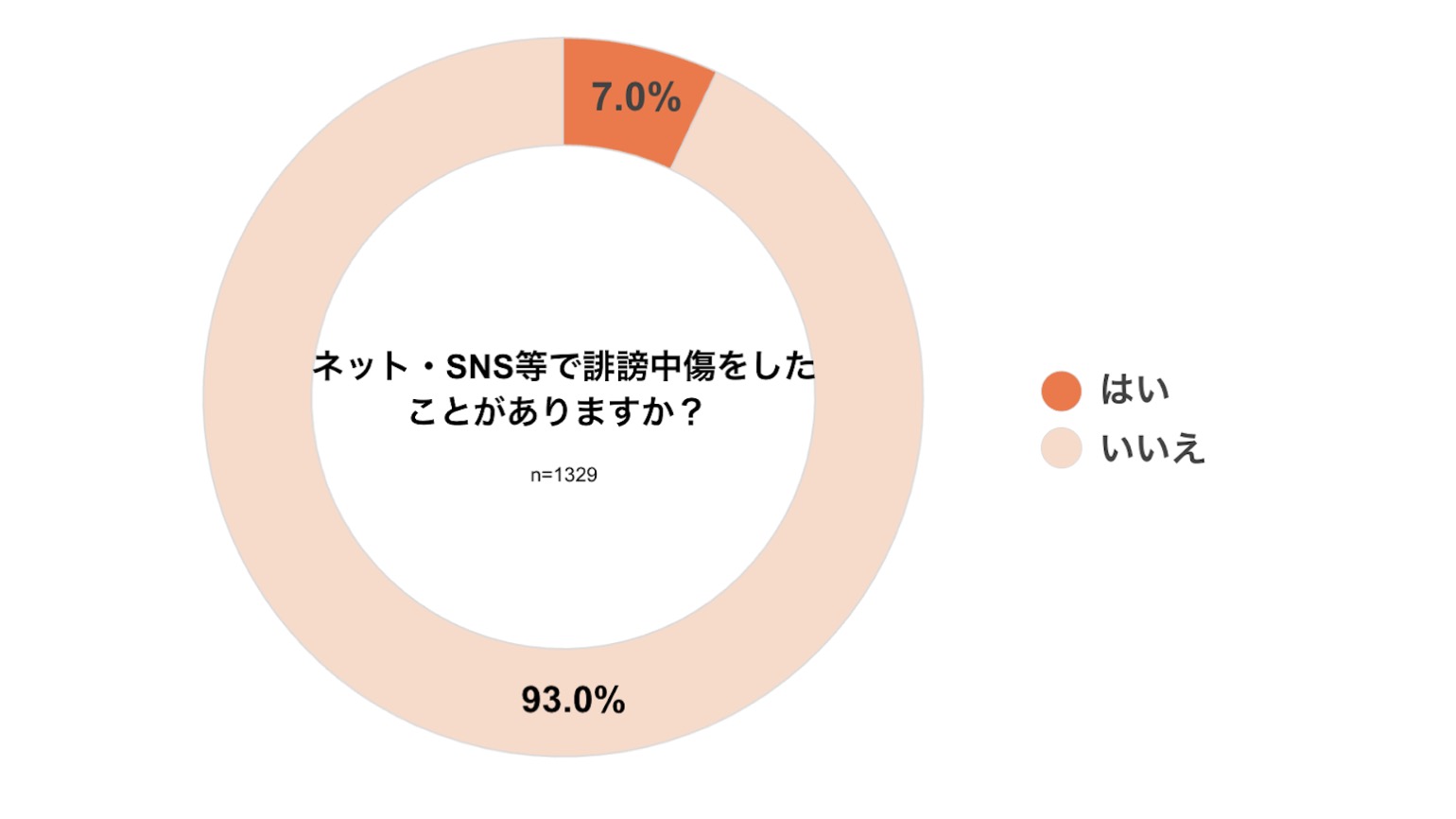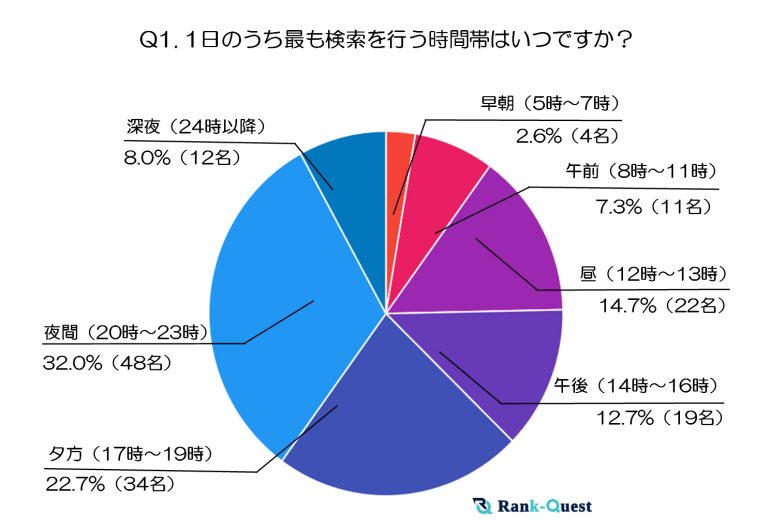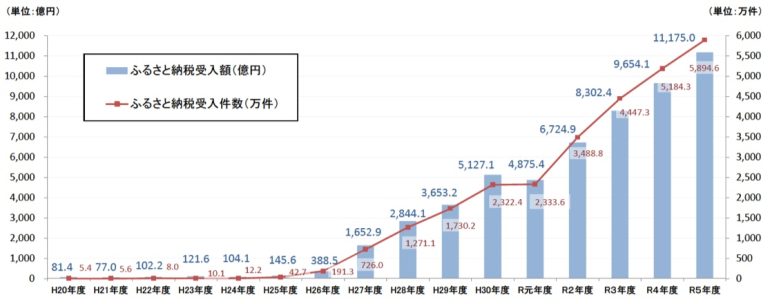カレンダーで『社日』という聞きなれない言葉を見たことはないでしょうか? 年に二回しかないため見逃すケースも多い「社日」ですが、意味を理解することで、日本の季節感や気候、ビジネス習慣などを知る役に経ちます。地域の行事やしてはいけないことなど、社日について詳しく解説します。
社日(しゃにち)っていったい何?言葉の意味や由来をチェック
社日の正しい読み方は『しゃにち』または『しゃじつ』です。まずは、社日の意味や言葉の由来を見ていきましょう。
社日とは春秋の二回、戊(つちのえ)の日に産土神(土地の神様)を祭る日
社日とは、春分・秋分のそれぞれに最も近い戊(つちのえ)の日のことです。春分と秋分は1年に1回ずつあるため、社日も年2回。春の社日を「春社(しゅんしゃ/はるしゃ)」、秋の社日を「秋社(しゅうしゃ/あきしゃ)」といいます。
春の社日は種まき、秋の社日は収穫の時期に当たり、社日は昔から農業において大切な日とされてきました。そのため、社日は土地の神様を祭る日として扱われ、各地域でさまざまな行事が催されています。
なお、戊の日は土と関係が深いため、十干(じっかん)の中で戊の日が選ばれるようになったとされています。
社日を祝う風習は中国が由来
社日を祝う習慣は、もともと中国にあったものです。かつて、中国では土地の守護神『社』を祭り、作物の豊穣を祈願する習慣がありました。
この習慣が中国から伝来すると、土地の神様を信仰する日本の風土と融合し、農業における重要な儀式として広まっていったといわれています。
戊を含む十干も、そもそも古代中国で生まれた数え方です。戊をつちのえと読むことからも分かるように、中国でも戊は土に関係する言葉として扱われていました。
なお、中国では社日が時代により異なり、たとえば唐代の社日は立春・立秋から5番目の戊の日です。
社日は日本の季節を把握するための「雑節(ざっせつ)」の一つ
『雑節(ざっせつ)』とは季節の変化を把握するために作られた暦のことです。二十四節気や五節供といった中国由来のものではなく、日本の文化に合わせて独自に作られました。
雑節にはいくつかの目印があり、社日もその一つです。いつを社日にするかは時代により違っており、春分・秋分の前後のどちらにするかで混乱していた時期もあります。
なお、社日以外で雑節の目印となっているのが、節分・土用・彼岸・八十八夜・二百十日・入梅・半夏生です。現代の生活でよく耳にする言葉も多く含まれています。
例えば、彼岸は春分の日・秋分の日を中日とする前後3日間を指す言葉です。現在の彼岸になったのは天保暦以後であり、かつては春分・秋分の翌々日を彼岸の入りとしていた時代もありました。
2024年・2025年の社日はいつ?
2024年の社日は、春の社日(春社)が3月15日、秋の社日(秋社)が9月21日となります。
2025年の社日は、春の社日(春社)が3月20日、秋の社日(秋社)が9月26日です。
社日は、雑節や二十四節気が書かれているカレンダーには載っていることが多いため、今まで意識したことがない方もチェックしてみてはいかがでしょう。
社日に行う地域ごとの行事
社日には全国各地で土地の神様を祭る行事が催されています。福岡県で行われる有名な行事と、全国的に行われている一般的な行事を紹介します。
社日祭として有名な福岡県の「お潮井取り(おしおいとり)」
福岡県で社日に毎年行われている恒例行事が、福岡市の筥崎宮(はこざきぐう)の年中行事『お潮井取り』です。春と秋にそれぞれ『春季社日祭』『秋季社日祭』として催されます。
お潮井取りは、五穀豊穣・除災招福・家内安全などを祈願するお祭りです。参拝客はお潮井取りの日に筥崎宮の境内にある箱崎浜の真砂を持ち帰り、玄関先や田畑にまいたり身に振りかけたりして、災難除けを願います。
箱崎浜の真砂は神聖なものとされており、社日の日にとった真砂は特に効き目があるといわれています。博多三大祭りの一つ『博多祇園山笠』でも、神事の無事を祈願して筥崎宮の真砂を取りにくるほどです。
全国的には「治聾酒(じろうしゅ)」や「社日詣(しゃにちもうで)」
社日に見られる全国的な習慣としては、お酒を土地の神様に供えたり、『治聾酒(じろうしゅ)』を飲んだりすることが挙げられます。治聾酒というお酒は存在せず、社日にお酒を飲むことで耳が良くなるといわれています。
いくつかの神社へ参拝する『社日詣(しゃにちもうで)』も、社日の風習の一つです。社日詣は全国で行われており、祭る神様は『御地神様』『御社日様』などと地域により異なります。
ほかにも、餅をついて神様を祭ったり特定の場所で神様に祈りを捧げたりと、地域ごとにさまざまな神事が行われています。
社日では何をする?お供え物や作法
社日の作法を知っておくと、社日についてより深く理解できるでしょう。社日に供えるものと社日にしてはいけないことを紹介します。
社日のお供え物は?
社日には米・日本酒・おはぎなどを供えるのが一般的です。通常は小皿で供えますが、地域によっては米を一升瓶に詰める場合もあります。ただし、社日の風習は地域色が強く反映されるため、供えるものや方法は各地域で異なります。
なお、かつての中国では春の社日に五穀の種子を、秋の社日には初穂を供えていたようです。日本でも土地の神様に、春には麦や米などを供え豊作を願い、秋には穀物の豊かな実りに感謝し、収穫を祝う目的で社日に初穂を供える地域があります。
社日にしてはいけないこと
社日に土を触ると、土地の神様を怒らせてしまうといわれています。畑作業・家庭菜園・ガーデニングは土を触ることになるため、社日に行うのはNGです。
社日に肉と魚を供えるのもタブーとされています。社日は土地の神様を祭る日であることから、米・野菜・種子などの農作物や、餅・お酒など農作物由来の物を供えるのが一般的です。
なお、1年に4回ある「土用(どよう)」の期間中も土を動かす土木工事や建築作業をしてはいけないとされており、社日のタブーも似たような考え方から生まれたといわれています。
社日に代表される暦に関わる言葉は、意味はもちろん読み方や言葉の由来も意外に知らない、という人が多いでしょう。
日本の気候に合わせて決められ、現在も風習として残っているに雑節は、知っておくと季節の変化を感じられたり、ビジネス習慣の理解に約だったりと役に立つ機会も多いはず。
暦関連の用語に興味がある人は、以下の記事もあわせてチェックしてみてはいかがでしょう。
うなぎは昔から、夏に精力をつけられるといわれる食べ物です。そして、『土用の丑の日』に食べることが一つの風習ともなっています。なぜこの日に、多くの人がうなぎを食す...
八十八夜は有名な童謡の歌詞にも登場し、日本人にとってなじみ深い日ですが、何をする日なのか正確に答えられる人は少ないでしょう。正しい意味を覚えておくと生活に役立ち...
「穀雨」とはどんな季節を表わす言葉?意味や由来から季節を感じてみよう
『穀雨』が季節を表す言葉であることは知っていても、読み方や、いつ頃を指すのか分からない人もいるでしょう。意味や読み方、時期などを紹介します。関係の深い二十四節気...
構成/編集部