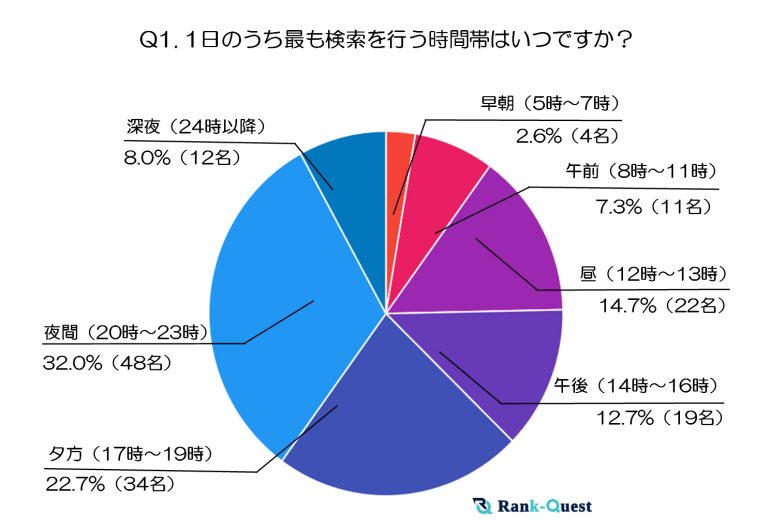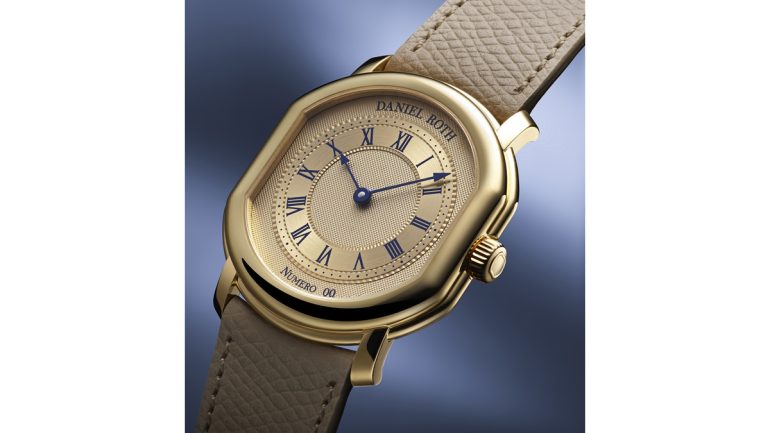人の話を遮って別の話を始める、『話の腰を折る人』に出会ったことはありませんか?『話の腰を折る』の意味から当てはまる人の特徴まで解説します。周囲に話の腰を折る人がいる場合の対処法も押さえて、人付き合いに役立てましょう。
「話の腰を折る」とはどんな言葉?
『話の腰を折る』というフレーズは、人の行動を表す慣用句の一つです。日常でもビジネスシーンでも使う場面があるので、正しい意味や言葉の成り立ちをチェックしておきましょう。
意味は「会話を遮り別の話をすること」
『話の腰を折る』とは、『相手の話を途中で遮って、別の話にすり替えてしまう様子』を表す言葉です。人の話を聞かず流れとは全く関係のない話題へと変える人を、『話の腰を折る人』と表現します。
第三者や相手だけでなく自らの行動に対しても使える表現です。第三者や相手の行動に対しては、「彼女は話の腰を折る癖がある」というように表します。
ビジネスシーンでは「話の腰を折るようですが…」と、発言の前置きをするクッション言葉としても使用できる表現です。
仕事の場で会話を中断することは失礼に当たるため、あらかじめ断ってから自分の意見や要件を言うと配慮が伝わります。
「腰」を重要な部分と考える表現
『話の腰を折る』の語源となったのは『腰を折る』という慣用句です。『腰』を重要な部分ととらえ、大切な取り組みを邪魔して続ける気をなくす行為を表します。
腰は胴体を支えており、歩く・座る・起き上がるなど体を動かすために欠かせない部位です。もしも腰を骨折してしまえば、日常生活に大きな影響が出るだけでなく一生自由に動けなくなるかもしれません。
体の大切な部分である『腰』を折ることを、『大事な部分をダメにする』行動にたとえて『腰を折る』と表現するのです。転じて、話の邪魔をして中断することを『話の腰を折る』と表すようになりました。
「話の腰を折る」の使い方と例文
具体的には、以下のようなシーンで使える言葉です。
会議中の発言を中断する場合
会議や打ち合わせなどで、誰かが話をしている最中に別の人が発言を遮ることがあります。このような場合、「話の腰を折る」という表現が使われます。
【例文】
・田中さんがプレゼンをしている時に、山田さんが突然質問をして話の腰を折ってしまった。
日常会話を中断する場合
日常の会話の中で、誰かが話している途中に別の話題を持ち出して中断させる場合にも使われます。こうした状況を「会話泥棒」と表現する場合もあるでしょう。
【例文】
・友達と旅行の話をしていたのに、急に別の友達が違う話題を振ってきて話の腰を折られた。
「話の腰を折る」の言い換えに便利な類語表現
「話の腰を折る」といっても伝わらない場合、こうした慣用句以外の表現方法を覚えておくと便利です。いくつか類語を紹介します。
話に割り込む
「割り込む」は、誰かが話している最中に無理に話に入っていく行動を指します。これにより会話の流れが中断されることが多く、場合によっては無作法と感じられることもあります。
【例文】
・彼が新しいプロジェクトについて話している最中に、佐藤さんが自分の意見を言おうとして割り込んできたので、話の流れが途切れてしまった。
話を遮る
「遮る」は、誰かの話を途中で止めたり、中断させたりする行動を指します。この表現は、意図的に話を止める場合によく使われます。
【例文】
・プレゼンの最中に上司が突然質問をして話を遮ったため、発表者は一瞬戸惑ってしまった。
これらの類語は、いずれも誰かが話している最中にその流れを妨げる行動を示す際に使われます。どちらの表現も、「話の腰を折る」と同様に、相手の話の連続性や流れを損なう行為を表すのに適しています。
話の腰を折る人の特徴

(出典) pexels.com
あなたのまわりには、いつも会話の途中で違う話をはさむ『話の腰を折る人』はいませんか?
どのような特徴や心理から半紙の腰を折ってしまうのかを理解すると、迷惑に思う言動にも納得がいくかもしれません。
自分中心の言動をしてしまう
話の腰を折る人はまわりの人に配慮せず、自分中心の言動をしてしまう傾向が強いようです。
誰かの話を聞くよりも「話を聞いてもらいたい」という気持ちが強いため、会話に参加している人や周囲の人の気持ちを考えられません。まわりから『わがままで身勝手な人』と認識されている場合も多いでしょう。
しかし、自らの発言にばかり焦点を当てているだけで、悪意がないケースも少なくありません。誰かを傷付ける意図はなくても、つい自分が興味のある話に持って行ってしまう癖がある人もいます。
人の話を最後まで聞くのが苦手
話の腰を折る人の多くは、落ち着いて人の話を最後まで聞くことが苦手です。
「あれも言いたい」「これも言いたい」と意識が内側に向かっているため、周囲の状況や人の気持ちを冷静に読み取れず自分本位に振る舞って場の空気を壊してしまいます。
自身に関係がない・興味が持てない話題であっても、多くの人は我慢して最後まで話を聞こうと努めるでしょう。
しかし、話の腰を折る人には『こらえて最後まで聞く』という行動が難しい傾向があります。
思ったことをすぐに実行したかったり、一つのことにじっくり取り組むのが苦手だったりすると、話の腰を折ってしまう頻度が高くなるでしょう。
話の腰を折る人への対処法

(出典) pexels.com
話の腰を折る人の特徴や心理を理解していても、実際に話題を中断されてしまうとストレスを感じる人は多いでしょう。
周囲に当てはまる人がいる場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
タイミングを見て話しを戻す
話の腰を折る人が話題を変えてしまったら、タイミングを見て話を戻しましょう。
話の腰を折ってしまう人は空気を読むのが苦手な傾向があるので、最初はこちらの意図に気づかず、なかなか上手くいかないかもしれません。
しかし、何度も軌道修正を繰り返せば、その人の傾向と対策が見えてくるはずです。
仕事関係や重要な話題で話を中断されると困る場合は、こちらも少々強気な発言が必要かもしれません。話を変えられそうになったら「まずはこの話題から進めませんか?」と、はっきり主張するのがポイントです。
話の腰を折る人が上司をはじめとした目上の相手であれば、まず相手の意見を聞き最後に自分の意見を述べるようにすると角が立ちにくくなります。
相手の話に付き合う
友人と会話しているときや家族との雑談で時間の制限がない場面なら、相手の話にただ付き合うのも対処法の一つです。
プライベートで話の腰を折ってしまう人はほとんどの場合、話すことに夢中になっているだけです。議論がしたいわけではないので、意見を求められるケースはまれでしょう。
話題をそらされたり中断されたりしても大きな支障がなければ、諦めて聞き流す程度にしておくとストレスを感じにくくなります。
肯定しながら話を聞いていれば、相手が「話を聞いてくれた」と満足して話題が終わるケースも少なくありません。
話の腰を折る癖を直したいと思ったら

(出典) pexels.com
話の腰を折る人の特徴を確認して、「自分に当てはまっているかも…」と不安になっている人もいるかもしれません。周囲の会話に別の話題を割り込む癖がある場合、どうすれば改善できるのかを見てみましょう。
発言する前に一呼吸置いて
自分が話の腰を折っていると感じたら、まずは思いつくままに勢いで話し始めるのをやめましょう。発言や行動する前に一呼吸置いて周囲の状況を気にかけるだけでも、話の腰を折ってしまう頻度はぐんと減ります。
最初は我慢が苦痛に感じるかもしれませんが、人間関係を円滑にするためのスパイスと考えるのがおすすめです。話す前に一呼吸する習慣が身に付けば、自然と冷静に言動を見直せるようになるでしょう。
『会話はキャッチボール』と改めて思い直してみるのも、話を折る癖の改善に効果的です。会話は1人だけでは成り立ちません。相手があるからこそ会話が成立すると考えれば、自分本位な発言を我慢する理由ができます。
相手の言葉に耳を傾ける
自分が話を聞いてほしいと思うように、会話をしている相手にも意図や感情があります。話の腰を折る癖を直したいと思ったら、まずは相手の気持ちを尊重して話を最後まで聞きましょう。
考えや感じ方が違うと、つい否定したくなるかもしれません。しかし、最後まで話を聞けば共感できる部分や疑問点など、さまざまな発見があるはずです。
相手の言葉に耳を傾けることで、相手の意図を理解しやすくなります。反対意見があるとしても、話を聞いた上で議論をすれば建設的な議論につながるでしょう。
また、「自分だけ話しすぎているな」と感じたときは、相手の話を引き出すような質問をすると会話のバランスが取りやすくなります。
構成/編集部