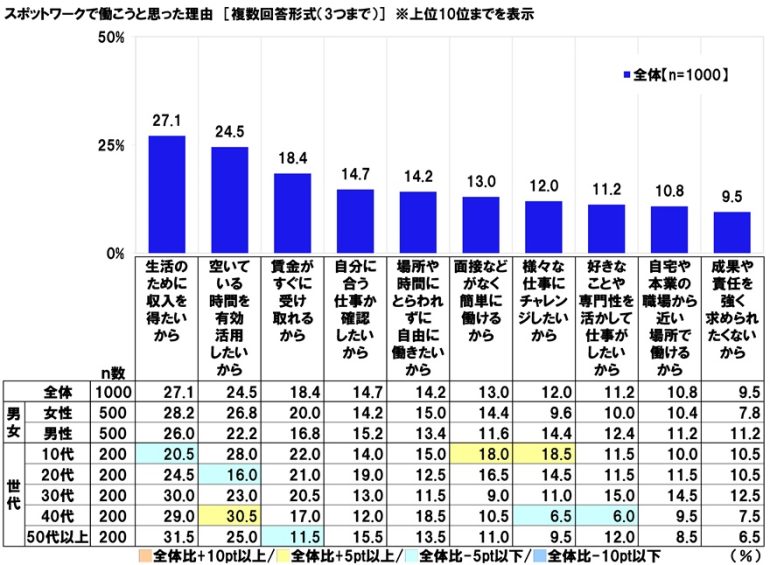「ナレッジ」とは?類義語との違いも解説
近年、ビジネスシーンや職場で、『ナレッジ』が付く用語を見聞きする機会が多いのではないでしょうか?ナレッジは、本来の意味とビジネス上の意味が異なります。まずは、ナレッジが持つ本来の意味を理解しましょう。
■「知識」を意味する和製英語
ナレッジは、英語の『knowledge』を語源とする和製英語です。意味は情報、知識のこと。
ちなみに和製英語とは、日本人によって作られた英語で、本来の英語とは少し異なるニュアンスをまといます。
【例文】
- 書籍や新聞から必要なナレッジを得た
- 自分には国際分野のナレッジが足りない
- ナレッジ不足で、話の意味が分からなかった
■「ノウハウ」との違いは経験しているかどうか
ナレッジに似た言葉に、『ノウハウ』があります。物事の手順・知識・技術などを意味する言葉で、know(知る)とhow(方法)を組み合わせた『know-how』が語源です。
ノウハウとナレッジはどちらも知識を意味しますが、微妙なニュアンスの違いがあります。ノウハウは、日本語でいう知恵や方法論のようなものであり、経験を通じて得られるものと考えられています。
ナレッジは、自分がその物事を経験しているかどうかはあまり関係がありません。主に、本や新聞、他人との会話などから得られる知識を指すと認識している人が多いかもしれません。ナレッジは言語化されているため、ノウハウに比べて他人と共有しやすいのが特徴です。
ビジネスでの「ナレッジ」の使い方と例文
ナレッジは、ビジネス用語の一つでもあります。ビジネスシーンや組織の中では、「単なる知識」を超えた価値あるものとして認識されています。例文を通じて、意味・使い方を理解しましょう。
■ビジネスで用いる「ナレッジ」の意味と使い方
ビジネスにおけるナレッジは、ただの知識や情報ではなく、『企業にとって有益なもの』や『付加価値のあるもの』を意味します。ビジネスに関する一般的な知識はもちろん、実体験からの学びや失敗例、成功例なども含まれる点に留意しましょう。
一人が経験できることには限りがありますが、それぞれがナレッジを共有すれば、組織全体の資産として活用できます。業務の効率化や利益の向上などに役立つことから、ナレッジの共有や活用を重視している企業は少なくありません。
■「ナレッジ」の例文
ビジネスでは、どのような文脈でナレッジが使われるのでしょうか?ミーティングやプレゼンテーションなどで恥をかかないように、ナレッジの正しい使い方を覚えましょう。
【例文】
- ベテラン従業員のナレッジを共有するために、専用のITツールを導入する予定だ
- 経験者採用を強化している理由の一つに、ナレッジの獲得が挙げられる
- ビジネス環境が急速に変化している現代、ナレッジを十分に活用する必要がある
- データベースにあるナレッジは、社員であれば誰でも自由に閲覧ができる
「ナレッジ」の重要性
企業がナレッジの蓄積や共有を重視するのには理由があります。ナレッジを有効活用すると、企業や従業員にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか?ナレッジの重要性を考えてみましょう。
■従業員の生産性が高まる
ナレッジの蓄積・共有は、生産性の向上に直結します。例えば、アイデア出しをする際、過去の失敗事例や成功事例、市場データなどに自由にアクセスできる環境を整えておけば、従業員は新たなアイデアを創出しやすくなるのがメリットです。
模範となる従業員の知識やノウハウをマニュアル化して共有した場合、従業員全体のスキルが底上げされます。問題がスピーディーに解決できたり、作業の効率化につながったりして、企業にプラスの効果がもたらされるでしょう。
人材の入れ替わりが多い企業では、人材育成に多くの労力が費やされます。蓄積・共有されたナレッジを活用することで、育成にかかる時間や労力を短縮できるほか、育成の質が一定に保たれます。
■特定の従業員に業務が依存するのを防ぐ
個々が業務で得た知識や情報を共有する仕組みを作れば、属人化によるリスクを未然に防げます。『属人化』とは、特定の従業員しか業務の詳細を把握できていない状態のことです。
担当者の不在時に業務が滞ったり、業務プロセスがブラックボックス化したりといった事態につながるため、属人化は何としてでも避けなければなりません。いくら優秀な業績を残せても、属人化した状態では再現性が著しく低く、いずれは組織全体にマイナスの結果をもたらすでしょう。
とりわけ属人化の回避が必要なのは、一貫性が求められるバックオフィス業務や顧客情報、トラブル対応の履歴などです。これらの情報は人に集約せず、組織として管理しましょう。
■業務の標準化により顧客満足度が向上する
ナレッジの蓄積・共有は、業務の標準化を促します。担当者間による質のばらつきがなくなるため、顧客満足度が向上するでしょう。必要な知識や情報を素早く引き出せるようにしておけば、スピーディーに対応できます。
企業のカスタマーサポートは、企業と顧客とをつなぐ窓口です。顧客に最も近い立場であり、ニーズやクレーム、感謝の言葉といった『顧客のリアルな声』に常に接しています。
カスタマーサポートのナレッジが、営業部や企画部などの他の部門に共有されれば、さらなる顧客満足度の向上が見込めるでしょう。
「ナレッジ」に関連するビジネス用語3選
ナレッジの重要性が認知されるのに伴い、ナレッジに関するビジネス用語が増えています。自分がその用語を使うかどうかは別として、会話の中で意味を理解できるようにしておく必要があります。
■知的労働者を指す「ナレッジワーカー」
『ナレッジワーカー』とは、自身が保有するナレッジにより、付加価値を生み出せる『知的労働者』のことです。マニュアル通りの作業を行うマニュアルワーカーと違い、自分の専門性や経験を武器とします。組織に属するナレッジワーカーもいますが、基本的に時間や場所にとらわれずに働けるのが特徴です。
代表的な職業としては、コンサルタント・金融アナリスト・データサイエンティスト・ITエンジニアなどが挙げられるでしょう。専門医や士業も、ナレッジワーカーに含まれます。
AIやロボットの台頭で、マニュアルワーカーの仕事は減少する可能性があります。一方、企業に対して付加価値を提供できるナレッジワーカーは、今後ますます注目されるでしょう。
■経営手法の1つ「ナレッジマネジメント」
『ナレッジマネジメント』とは、ナレッジを組織全体で活用する経営手法です。
ナレッジの共有により、生産性の向上や属人化の解消に期待できるほか、組織を成長させる新たな価値が生まれる可能性があります。ナレッジに基づいた迅速な意思決定ができるため、機会損失を避けられるでしょう。
ナレッジマネジメントの重要な概念が、『暗黙知』と『形式知』です。暗黙知とは、個人的な経験に基づく『言語化されない知識』です。形式知とは、文章・図表・数式などで説明された『誰にでも理解できる知識』を指します。
ナレッジマネジメントとは、暗黙知を形式知に変換し、ナレッジとして共有・活用する方法といえるでしょう。人材の流動性が増す中、ナレッジマネジメントが機能していない組織では、人材の流出とともに重要な知識やノウハウが失われてしまいます。
■企業の知的資産「ナレッジベース」
『ナレッジベース』とは、業務に関する知識・情報をデータベース化したものです。個人の暗黙知を全体の形式知に変換し、システム上に記録したものと考えましょう。企業の知的財産であり、基本的にアクセスできるのは従業員のみです。
ナレッジベースを構築すると、従業員は知りたい情報をすぐに手に入れられます。追加や編集が可能な状態にしておけば、知識や情報の陳腐化を防げるでしょう。
ナレッジベースの構築方法として、Excelなどの既存ツールを使う方法と、外部ツールを活用する方法があります。時間とともにナレッジの量は膨大になるため、専用の外部ツールを使う方が便利です。
ビジネスで注目される「ナレッジ」
ナレッジは本来、知識や情報を意味する和製英語ですが、ビジネスにおいては、企業に付加価値を与えるものを指します。
ナレッジという知的財産を多く有する企業ほど、市場での競争力を向上・維持できるといってもよいでしょう。
ナレッジは蓄積されても、活用できなければ意味がありません。近年はナレッジを活用するためのデジタルツールが次々と登場しています。
ビジネスにおけるナレッジの共有や活用は、今後ますます注目されるはずです。この機会に、企業におけるナレッジの重要性や生かし方を考えてみてはいかがでしょうか?
構成/編集部