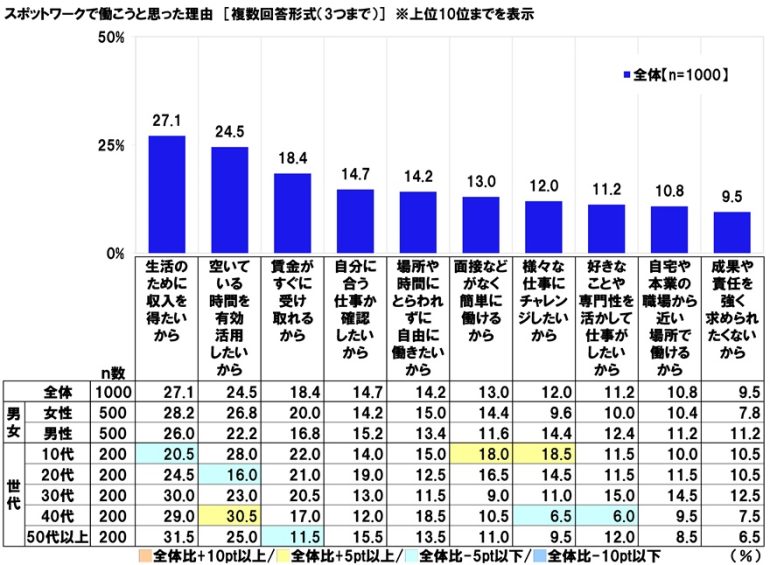入社した時にはやる気でみなぎっていた人が、徐々にやる気をなくしていく……。それは、リーダーや周囲の些細な言動が原因かもしれません。
社員のモチベーションが低下する職場風土の改善には、実は「関係密度」がカギになるのだそう。この「関係密度」とは何なのか、そして高めるポイントとは?
700を超える企業の職場風土改善に関わってきた中村英泰さんの著書『社員がやる気をなくす瞬間 間違いだらけの職場づくり』から一部を抜粋・編集し、〝社員のやる気を奪う間違った職場づくり〟を打破するヒントを紹介します。
ミスをしたときこそ「関係構築力」を発揮する
職場で起きるミスの大小で、上司の関係構築力がどの程度発揮されているかがわかります。
そもそも、職場では他人同士が、抽象的な概念をコミュニケーションという精度の低い道具を用いて仕事に向かっています。
さらに、第2章の「関係密度」を説明するときに確認をした、サイロ・スラブ・バウンダリーといった3つの距離に発生する「心理的な溝」が原因となって、失敗は、起こるべくして起こります。
それを端的に示しているのが、ハインリッヒの法則です。
ハインリッヒの法則は、労働災害における経験則の1つで、1件の重大事故の背後には重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が、さらにその背後には事故寸前だった300件の異常が隠れていることを明らかにしています。
1件の重大事故は、300件のヒヤリハット(予想外の出来事にヒヤリとしたり、ミスで事故を起こしそうになってハッとしたりすること)を1件1件解消していくことで発生を防ぐことができるというわけです。
そして、ヒヤリハットの原因の多くは、抽象的なコミュニケーションを背景としたヒューマンエラーが原因があるとされています。
職場のヒューマンエラーは「関係密度」を高めることで解消に向かいます。
とすると、部下のミスが増えているのであれば、上司が気にするのは接触の量と質をもとにした「関係密度」を高めることに注力すればよいのです。
☆ ☆ ☆
いかがだったでしょうか?
社員のやる気を左右する「関係密度」が高くなると、「社員の不本意な離職率が低下する」「コミュニケーションの齟齬が減る」「他責志向が、自己課題自己解決型に向かう」などのメリットがあるそうです。
部下や後輩との接し方に悩んでいる人は、心地良い職場づくりのヒントが詰まった一冊『社員がやる気をなくす瞬間 間違いだらけの職場づくり』をぜひ書店でチェックしてみてください。
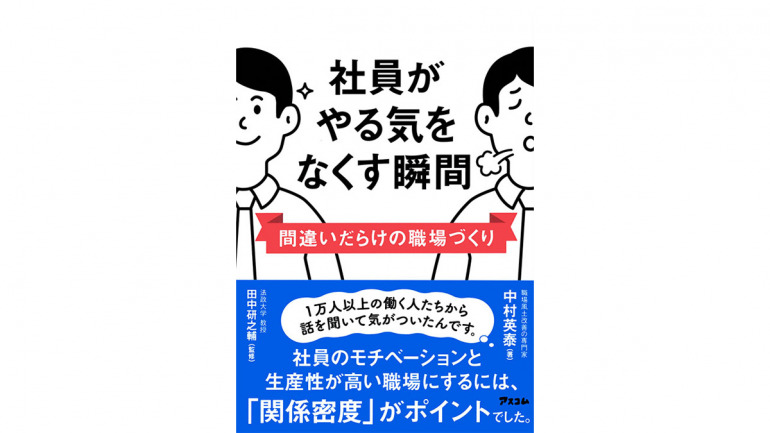 社員がやる気をなくす瞬間
社員がやる気をなくす瞬間
間違いだらけの職場づくり
発行所/株式会社アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
著者/中村英泰(アスコム)
株式会社職場風土づくり代表
ライフシフト大学 特任講師
My 3rd PLACE 代表
1976年生まれ。東海大学中退後、人材サービス会社に勤務したのち、働くことを通じて役に立っていることが実感できる職場風土を創るために起業し、法人設立。年間100の研修や講演に登壇する実務家キャリアコンサルタント。
監修/田中研之輔