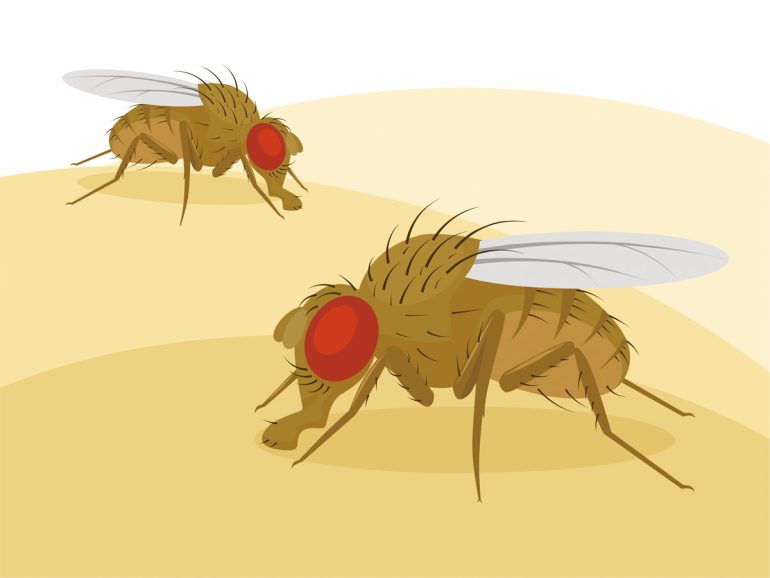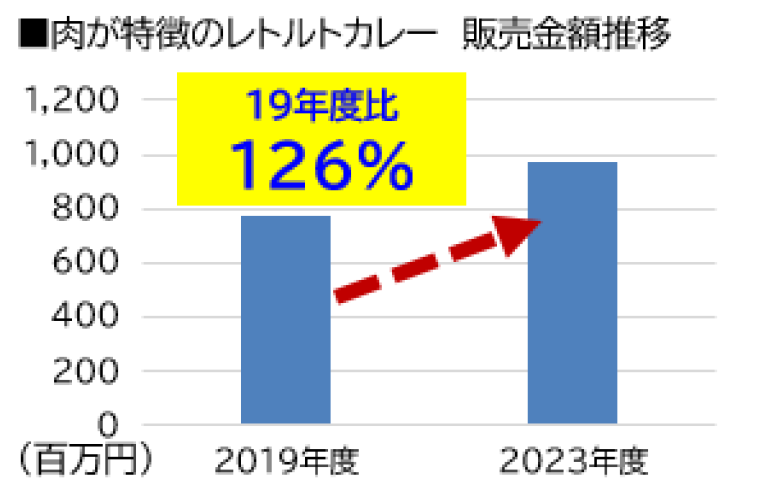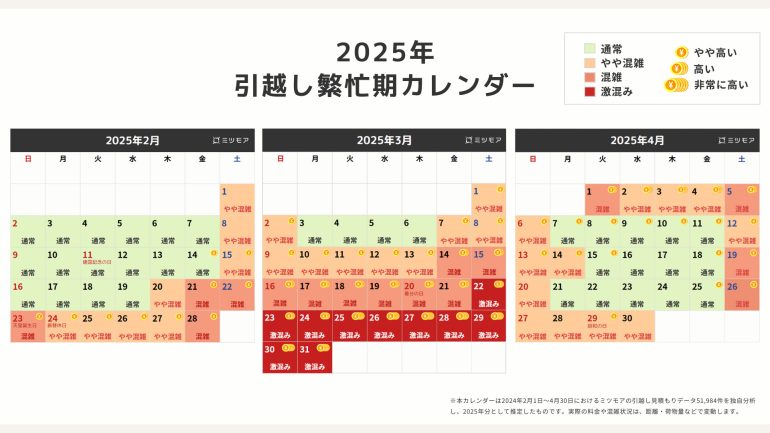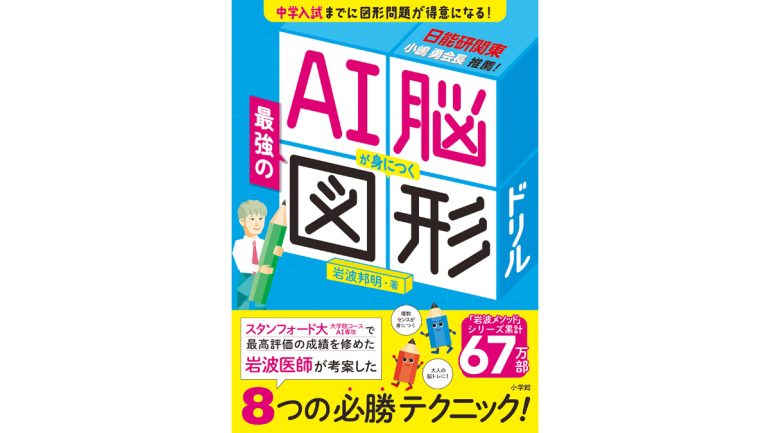жңҖиҝ‘гҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®зөҢжёҲиӘҢгҖҢForbesгҖҚгҒ§гҖҒгҖҢгғ©гғғгғ—еӯҗиӮІгҒҰпјҲplastic wrap parentingпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғ©гғғгғ—гҒ§еӯҗгҒ©гӮӮгӮ’еҢ…гҒҝиҫјгӮҖгӮҲгҒҶгҒӘгҖҒйҒҺдҝқиӯ·гҒӘеӯҗиӮІгҒҰгӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ’иЎЁгҒҷиЁҖи‘үгҒӘгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ гҖӮ
иӢұиӘһеңҸгҒ§гҒҜд»–гҒ«гӮӮгҖҒй ӯдёҠгӮ’гғӣгғҗгғӘгғігӮ°гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгҒ®з”ҹжҙ»гӮ’еёёгҒ«зӣЈиҰ–гҒҷгӮӢгҖҢгғҳгғӘгӮігғ—гӮҝгғјгғҡгӮўгғ¬гғігғҲпјҲhelicopter parentпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгӮҲгҒҸиҒһгҒӢгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғҮгғігғһгғјгӮҜзҷәзҘҘгҒ®иЁҖи‘үгҒ«гҒҜгҖҒж°·дёҠгҒ®гӮ№гғҲгғјгғігҒ®йҖІи·ҜгӮ’гғ–гғ©гӮ·гҒ§гҒӘгӮүгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгҒҢйҖІгӮҖйҒ“гӮ’гҒӘгӮүгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҢгӮ«гғјгғӘгғігӮ°гғҡгӮўгғ¬гғігғҲпјҲcurling parentsпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиЁҖи‘үгҒҢи©ұйЎҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжө·еӨ–гҒЁеҗҢж§ҳгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮйҒҺдҝқиӯ·гӮ„йҒҺе№ІжёүгҒӘеӯҗиӮІгҒҰгҒ«иӯҰйҗҳгҒҢйіҙгӮүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«йҒҺдҝқиӯ·гҒЁгҒҜгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢжңӣгӮҖгҒ“гҒЁгӮ’еӨұж•—гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгҒ№гҒҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒӮгҒ’гӮӢиЎҢзӮәгҒ§гҖҒйҒҺе№ІжёүгҒЁгҒҜгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢжңӣгӮҖгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒиҰӘиҮӘиә«гҒҢжңӣгӮҖгҒ“гҒЁгӮ’еӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гӮ„гӮүгҒӣгӮӢиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҒжң¬жқҘгҒҜеӯҗгҒ©гӮӮиҮӘиә«гҒҢйҒёгҒігҖҒиӢҰйӣЈгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеӯҗгҒ©гӮӮиҮӘиә«гҒ®еҠӣгҒ§д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒ№гҒҚзү©дәӢгӮ’гҖҒиҰӘгҒҢиӮ©д»ЈгӮҸгӮҠгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеӯҗиӮІгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒйҒҺдҝқиӯ·гӮ„йҒҺе№ІжёүгҒӘеӯҗиӮІгҒҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
йҒҺдҝқиӯ·гҒӘеӯҗиӮІгҒҰгҒ§гҒҜгғҸгғјгғүгғ«гӮ’и¶ҠгҒҲгӮӢеҠӣгҒҢиә«гҒ«гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„
в– гҒқгҒ®е ҙгҒқгҒ®е ҙгҒ®еӯҗгҒ©гӮӮгҒ®ж„ҹжғ…гҒ«жҢҜгӮҠеӣһгҒ•гӮҢгӮӢиҰӘгҒҹгҒЎ
д»ҘеүҚгҖҒеЎҫзөҢе–¶иҖ…гҒ«еҸ–жқҗгӮ’гҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгҖҢдҝқиӯ·иҖ…гҒ®йҒҺдҝқиӯ·гӮ„йҒҺе№ІжёүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®еӯҰеҠӣгҒҢдјёгҒіжӮ©гӮҖгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒҜгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҰеҮәгҒ—гҒҹе®ҝйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢеҲҶйҮҸгҒҢеӨҡгҒҸгҒҰеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢиӢҰз—ӣгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжёӣгӮүгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЁйҖЈзөЎгҒҢжқҘгӮӢгҖӮдҝқиӯ·иҖ…гҒҜеӯҗгҒ©гӮӮгҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒеЎҫгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиҰҒжңӣгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ гҒҢгҖҒеЎҫеҒҙгҒӢгӮүгҒ—гҒҹгӮүгҖҢгҒ“гҒ®еӯҗгҒӘгӮүгҒ§гҒҚгӮӢгҒҜгҒҡгҖҚгҖҢгҒ“гӮҢгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгӮҢгҒ°гғ¬гғҷгғ«гӮўгғғгғ—гҒ§гҒҚгӮӢгҒҜгҒҡгҖҚгҒЁе®ўиҰізҡ„гҒ«еҲӨж–ӯгҒ—гҒҰе®ҝйЎҢгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
дҝқиӯ·иҖ…гҒ®иҰҒжңӣгҒ«еҫ“гҒҲгҒ°еӯҰеҠӣгҒ®дјёгҒігҒҜжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгғҶгӮ№гғҲгҒ®зӮ№гҒҢдёӢгҒҢгӮҢгҒ°гҖҢгӮӮгҒЈгҒЁеҺігҒ—гҒҸгҒ—гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЁж–°гҒҹгҒӘиҰҒжңӣгҒҢжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзӣ®гҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘе…·еҗҲгҒ«гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҖҒе®ҹгҒҜеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®гҒқгҒ®е ҙгҒқгҒ®е ҙгҒ®ж„ҸиҰӢгҒ«жҢҜгӮҠеӣһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҖӮдёӯй•·жңҹгӮ№гғ‘гғігҒ§иҰӢгӮӢгҒЁеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„иҰҒжңӣгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒҸгӮӢдҝқиӯ·иҖ…гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ гҖӮ
зӯҶиҖ…гӮӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§10е№ҙй–“гҖҒеӯҰзҝ’ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒЁеӯҰеҠӣгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиҰӘгҒ®и·қйӣўж„ҹгҒ«гӮҲгӮӢеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ
зӣҙиҝ‘гҒ®гғҶгӮ№гғҲгҒ§зҗҶ科гҒ®зӮ№ж•°гҒҢдҪҺгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒЁи©ұгҒ—еҗҲгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҗҶ科гҒҢиӢҰжүӢгҒӘгҒ®гҒ§йҮҚзӮ№зҡ„гҒ«ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҒӢгҖҚгҒЁйҖЈзөЎгҒҢжқҘгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҶгӮ№гғҲгҒ®еҶ…е®№гӮ’гӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒиЁҲз®—гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘе•ҸйЎҢгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒеҲҶж•°гҒ®иЁҲз®—гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒҢгҒҹгӮҒгҒ«жӯЈи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҒҜж•°еӯҰгҒ®еңҹеҸ°гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢиә“гҒҚгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҢд»ҠеәҰгҒҜзӮ№ж•°гҒҢдёҠгҒҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж—©гҒҸгҒӢгӮүдәҲзҝ’гӮ’гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮгҖҒbeеӢ•и©һгҒЁдёҖиҲ¬еӢ•и©һгҒ®дҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒеҸ—еӢ•ж…ӢгӮ„е®ҢдәҶеҪўгҒӘгҒ©гӮ’дҪҝгҒ„гҒ“гҒӘгҒӣгӮӢгҒҜгҒҡгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢгӮ„гӮӢж°—гӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°зөҗеұҖгҒқгҒ®еӯҗгҒҜгҖҢеӢүеј·гҒ—гҒҰгӮӮгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжҠ•гҒ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҹәзӨҺе•ҸйЎҢгҒ®гӮ№гғўгғјгғ«гӮ№гғҶгғғгғ—гӮ’иёҸгӮ“гҒ гҒҶгҒҲгҒ§еҝңз”Ёе•ҸйЎҢгӮ’еҮәгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢгҖҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫ家еәӯгҒ§и©ұгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒгҖҢгҒҶгҒЎгҒ®еӯҗгҒҜгҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӯҰеҠӣгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйӣЈгҒ—гҒ„е•ҸйЎҢгҒҜеҮәгҒ•гҒӘгҒ„гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҚгҒЁиҰҒжңӣгҒҢжқҘгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
жҢҮе°ҺгҒ—гҒҹ1жҷӮй–“гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢи§ЈгҒ‘гҒҡгҒ«гҖҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгӮӮгҖҒдҪ•еәҰгӮӮз№°гӮҠиҝ”гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§ж…ЈгӮҢгӮҢгҒ°и§ЈгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®е•ҸйЎҢгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒжҢ‘жҲҰгҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһиӮўгӮ’гҒЁгӮҢгҒ°гҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮгҖҢгҒҶгҒЎгҒ®еӯҗгҒҜгҒқгӮ“гҒӘгҒ«еӯҰеҠӣгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒҫгҒҫгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
иҰӘгҒҢгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®иғҪеҠӣгҒ®йҷҗз•ҢгӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҢеӮ·гҒӨгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«жҢ‘жҲҰгӮ’гҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮ“гҒӘгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ
в– е®үеҝғж„ҹгӮ„ж„ӣжғ…гҒЁгҖҒеӨ–гҒ§гҒ®жҢ‘жҲҰгӮ„еҶ’йҷәгҒЁгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢйҮҚиҰҒ
дёҠиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ„ж„ҹжғігӮ’иҰӘгҒҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒЁгӮүгҒҲгҒҰгҖҒеЎҫгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиҰҒжңӣгӮ’еҮәгҒҷдҫӢгҒҜгҖҒйҒҺдҝқиӯ·гҒ®гҒ»гҒҶгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
еӯҗгҒ©гӮӮгҒЁдёҖз·’гҒ«еӯҰзҝ’гҒ®жҲҗжһңгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гӮҠгҖҒгҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒӢгӮ’家ж—ҸгҒ§иҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҒЁгҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒеҮәгҒҰгҒҚгҒҹи§Јжұәзӯ–гҒҢгҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒ®гҒқгҒ®е ҙгҒ®ж„ҹжғ…гҖҚгӮ„гҖҢеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«еӨұж•—гҒ•гҒӣгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҰӘгҒ®ж„ҹжғ…гҖҚе„Әе…ҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒгҒ„гҒ„зөҗжһңгӮ’з”ҹгҒҫгҒӘгҒ„гҒ©гҒ“гӮҚгҒӢйҖҶеҠ№жһңгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгҖӮ
еӯҰеҠӣгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҢеҗҢе№ҙд»ЈгҒ®еӯҗгҒЁи©ұгҒҷгҒ®гҒҢиӢҰжүӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гҖҒгҖҢгҒ§гҒҜеҗҢе№ҙд»ЈгҒ®еӯҗгҒЁй–ўгӮҸгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒӢгӮүгҒҜгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸйҒ гҒ–гҒ‘гӮҲгҒҶгҖҚгҒЁиҰӘгҒҢз’°еўғгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еӯҗгҒҜгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮиӢҰжүӢгҒӘзҠ¶жіҒгҒӢгӮүжҠңгҒ‘еҮәгҒӣгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
гҖҢзүҮд»ҳгҒ‘гӮ„жҺғйҷӨгҒҢиӢҰжүӢгҖҚгҒӘеӯҗгҒ®йғЁеұӢгӮ’иҰӘгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁжҺғйҷӨгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гҒҰгҒ„гҒҹгӮүгҖҒж°ёйҒ гҒ«зүҮд»ҳгҒ‘гӮ„жҺғйҷӨгҒ®зҝ’ж…ЈгҒҜиә«гҒ«гҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜиҰӘгҒҢгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁи©ұгӮ’иҒһгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҖҒиӢҰжүӢгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ家еәӯгҒёгҒ®е®үеҝғж„ҹгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е®үеҝғж„ҹгҒҢгҒӘгҒ„гҒҢгӮҶгҒҲгҒ«гҖҒйқһиЎҢгҒ«иө°гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиҮӘе·ұиӮҜе®ҡж„ҹгӮ’иӮІгӮҒгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгӮӮеӨҡгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒиҰӘгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№ж„ҹиҰҡгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
еӯҗгҒ©гӮӮгҒ®и©ұгҒҜиҒһгҒҚгҖҒй ӯгҒӢгӮүеҗҰе®ҡгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’йөңе‘‘гҒҝгҒ«гҒ—гҒҰзү©дәӢгӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖӮеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜеӨҡе°‘иӢҰгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҖҒгҒӨгӮүгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе®үеҝғгҒ—гҒҰйҒҺгҒ”гҒӣгӮӢ家гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒҜгҒӯгҒ®гҒ‘гӮӢеҠӣгҒҜгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁиӮІгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒҜгҒҡгҒ гҖӮ